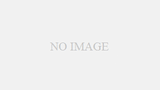刑務官とは、刑務所や拘置所などの矯正施設内において、受刑者の矯正処遇業務および施設内の治安維持を担う、法務省所属の法務事務官です。
刑務官には、矯正施設内に限定して、規律違反に対する処分権限である「戒護権」や、犯罪に対する「捜査権」といった法執行上の権限が与えられます。
通常、刑務官は紺色の制服と制帽を着用し、携行品としては捕縄(ほじょう)、呼び笛、刑務官手帳をポケットに収めております。
ただし、捜査活動や緊急時には、特殊警棒やけん銃の携行・使用も認められています。
刑務官の各種任務
刑務官の主な任務は、各矯正施設の中で受刑者の監視や処遇を行い、施設内の秩序と安全を維持することです。
武道拝命(武拝)と特別警備隊
警察官の採用試験では、プロボクサーや相撲取りくずれなど、闘技の実績を持つ人物を加点の対象としたり、柔道・剣道の有段者を「武道指導者枠」として採用する制度が存在します。
刑務官にも類似した制度があり、武道に秀でた男性の有段者を「武道拝命(通称:武拝)」として採用する仕組みがあります。この「武拝刑務官」は、受刑者の間でも“怖い”存在として知られています。
そして、これら武拝刑務官を中心に編成されているのが、管区矯正局によって設置される刑務所内のセキュリティ部隊、「特別警備隊」です。
警備隊の隊員は、通常の刑務官とは異なる濃紺の出動服と編み上げ靴を着用し、常時、警棒によって武装しています。一般の刑務官が非武装であるのに対し、特別警備隊員は武装しており、その名のとおり、警察の機動隊に相当する役割を果たしています。
特別警備隊は刑務所単位ではなく、管区ごとに編成されており、同管区内の別の刑務所で暴動や逃走事件が発生した際には、応援部隊として現場に派遣される体制が整っています。
特別警備隊の実態
平常時、特別警備隊員は一般の刑務官とともに矯正施設内に配置され、所内の秩序や規律の維持にあたっています。ただし、彼らは普段あまり目立たず、施設内のあちこちに“潜伏”しているため、受刑者が彼らの存在を意識することは少ないようです。
しかし、ひとたび受刑者による喧嘩や暴動が発生すれば、刑務官の警笛が「ピリリ」と鳴ったその瞬間、どこに隠れていたのかと思うほどのスピードで、特別警備隊が出動服姿で駆けつけ、暴れる受刑者を多数で取り囲み、制圧・連行します。
連行の際には、受刑者をうつ伏せにして両手両足を数人の隊員が持ち上げる、いわゆる「飛行機」と呼ばれるスタイルが用いられます。もちろん、受刑者に対する暴力行為は認められておりませんが、抵抗する受刑者が暴れた場合、不可抗力により床に落ちることもあり、それが受刑者にとって抑止力となるようです。
このような任務の性質上、特別警備隊の隊員には、威圧感のある体格を備えた者が多数です。
拘置所と死刑制度について
刑務所とは、刑が確定した受刑者を収容し、服役させるための矯正施設であり、更生の機会を提供する場です。受刑者の更生を支援するのが刑務官の職務ですが、死刑の執行を担うのもまた刑務官です。
一方で拘置所とは、刑が確定していない未決拘禁者(未決囚)や、すでに刑が確定しているものの、刑務所へ移送されるまでの間の既決拘禁者(既決囚)を留め置くための施設です。
意外に思われるかもしれませんが、未決囚の生活は比較的自由です。たとえば、毎日お菓子を食べることができ、本を好きなだけ読むことも可能です。
特に嬉しい点として、刑務所と異なり、強制労働が課せられない点が挙げられます。未決囚は私服の着用や頭髪の自由が認められており、合法的に「ニート」のような生活が可能です。
さらに、面会や手紙のやり取りも平日であれば毎日可能です。これは、刑務所での「月に数回」といった厳しい制限と比べ、大きな違いです。
また、食事は質素ながら無料で提供されますし、自分の持ち金があれば出前を取ることもできます。
たとえば、東京拘置所では100種類以上の食品に加え、衣類やマンガ、布団、お金なども、家族や知人からの差し入れが可能です。
このように、拘置所は刑務所と比べると大きく優遇されています。
しかし、こうした自由な側面とは裏腹に、拘置所は死刑の執行が行われる場所でもあります。つまり、天国のような一面を持ちながら、地獄のような現実も抱えているのです。
拘置所には、未決囚や既決囚に加えて、死刑囚も収容されています。彼らは裁判所から更生のチャンスを与えられず、死刑が確定した人々です。
死刑は、それ自体が刑罰であるため、死刑囚に懲役などの労働は課せられません。つまり、死刑囚は刑務所に送られることなく、そのまま拘置所内で、死刑が執行されるその日まで留め置かれることになります。
死刑囚は通常、単独房に収容されており、日々は読書や写経などで過ごすことが多いですが、希望すれば軽作業を行うこともあります。
ただし、部屋は非常に狭く、動き回るスペースも限られています。死刑囚たちは、死刑の恐怖から精神的な不安を抱えることが多く、さらに運動不足による健康問題も懸念されています。
また、未決囚とは異なり、死刑囚への外部からの差し入れは厳しく制限されていることが多いです。
たとえば、和歌山毒物カレー事件で死刑判決を受けた林真須美死刑囚の場合、外部との接触が極端に制限され、面会さえ認められない状況が続きました。
この措置について林死刑囚側は違法であるとし、国に対して慰謝料の支払いを求める裁判を起こし、判決も出されています。
ただし、多くの死刑囚は、差し入れがほとんどなく、日用品の多くを官給品(官物)でまかなっているのが現状です。
アメリカでは、死刑執行の直前に「最後の晩餐」として希望する食事が提供される慣習があります。
たとえば、ステーキを食べて最期を迎えたいという希望がよく聞かれます。一方、日本ではそのような配慮は一般的ではありません。日本の拘置所においては、死刑執行直前に、祭壇に供えられたお菓子を食べることが許される程度の温情にとどまっています。
また、アメリカでは死刑執行に被害者遺族が立ち会うことが認められていますが、日本ではこれが認められていません。なお、刑務所の中にも死刑を執行する設備を備えた施設が存在しています。
死刑の執行には、刑務官のほか、医師、検察官、検察事務官などが立ち会います。元検察官であり、後に弁護士として活躍した佐賀潜氏は、自身の著書『刑法入門』の中で、検事時代に担当でもないのに死刑執行に興味本位で立ち会ったことを記しています。
なお、佐賀潜氏は1969年に放映された日本初の法律系アニメ『六法やぶれくん』の原作者。この作品は漫画『カバチタレ!』のような法務アニメの先駆けであり、刑法や民法の知識を取り入れたユニークな作品でした。
裁判所と刑務官の関わり
裁判所も法務省の管轄であるため、裁判所から拘置所や刑務所への被告人の移送は、刑務官の任務の一つです。
刑事事件の公判中には、被告人が暴れないように、刑務官がその両脇をしっかりと固めています。仮に被告人が突発的に暴れた場合は、刑務官によってすぐに取り押さえられます。
一方で、裁判官が親の命を奪った被告人に対して優しい言葉をかけたことで、被告人だけでなく傍聴席、そして屈強で厳めしい刑務官までもが思わず涙ぐみ、「刑務官までもがホロリと涙を流した」と話題になり、ニュース記事になったこともあります。
脱獄に対する刑務官の対応
刑務所の構造は、鉄の扉や高い塀、コンクリートの床、監視カメラなど、脱獄を困難にする設計となっており、脱走を成功させるには刑務官の買収や外部協力者の存在が必要になると考えられます。実際、アメリカでは刑務官が買収される事例が多く、脱獄も珍しくありません。
日本でも昭和中期から後期にかけては、脱獄事件が頻繁に発生しており、刑務官が殉職したケースも存在します。
たとえ脱走が成功したとしても、刑務官に暴行を加えれば公務執行妨害、施設の破損は器物損壊、支給された衣類を着たまま逃げれば窃盗など、さまざまな罪が加算されるため、脱獄には何のメリットもありません。
通常、脱走犯の追跡や捜査は都道府県警察が行いますが、刑務官にも脱獄した受刑者を逮捕状なしで逮捕する権限が認められており、48時間以内であれば捜査も可能です。
とはいえ、現代の刑務所は監視カメラに加えて各種センサーなども導入されており、脱獄はほぼ不可能となっています。
ただし、2012年に広島刑務所で実際に懲役23年の受刑者が脱走した例があり、その際は工事用の足場が外壁に設置されていたことが原因でした。追跡には同刑務所の刑務官も参加しています。
刑務官の待遇と勤務環境
刑務官は公安職公務員であり、警察官や自衛官、海上保安官と同様に、一般の国家公務員とは異なる「公安職俸給表」によって給与が定められており、その額は比較的高額です。一方で、労働基本権は制限されており、労働組合の結成やストライキなどの行為は認められていません。
勤務については、基本的に一度出勤すれば勤務時間中は刑務所の中で過ごします。不要な外出はできませんが、受刑者の移送や連絡業務などで外に出ることはあります。
また、受刑者が外部の病院へ入院する場合には、交代要員を含めて6人態勢で24時間監視を行う必要があります。こうした厳しい勤務体制が、刑務官の職務の一端を表しています。
女性刑務官と女子刑務所
女性刑務官は、女性受刑者が抱える摂食障害や妊娠・出産といった、女性特有の問題にも向き合わなければなりません。そのため、精神的な負担が大きく、離職率の高さが問題となっています。実際、2017年度における女性刑務官の離職率は34%にのぼっています。
現在、日本には女性受刑者専用の刑務所(女子刑務所)が5ヶ所存在しており、それぞれは以下の通りです。
| 女子刑務所名 | 所在地 |
|---|---|
| 栃木刑務所 | 栃木県 |
| 笠松刑務所 | 岐阜県 |
| 和歌山刑務所 | 和歌山県 |
| 岩国刑務所 | 山口県 |
| 麓刑務所(支所) | 鹿児島県 |
笠松刑務所では、美容師の職業訓練が実施されており、女性受刑者が社会復帰に向けた技能を身につけられるよう配慮されています。
女子刑務所では、男子刑務所と同様にいじめの問題が存在しており、トイレに手紙や私物を流すなどの嫌がらせも報告されています。刑務作業は縫製や金属部品(ハーネス)の組立作業が中心で、女性受刑者たちが刑務官の制服や警備服の製造にも携わっています。
男子刑務所と異なり、女子刑務所では受刑者の罪状によって収容先を決めておらず、また「母子像」が設置されているなど、女性ならではの心情に寄り添った環境づくりが行われています。
女子刑務所においても高齢化は進んでおり、平成22年には60歳以上の受刑者が全体の約15%だったのに対し、平成25年には25%にまで増加。このような状況を受け、高齢受刑者に対応した施策も求められています。
刑務官以外の刑務所職員
刑務所には、様々な刑で収容された受刑者がいますが、刑務所の運営や公務の執行を担う主体は、言うまでもなく刑務官。
一方で、様々な受刑者に対応するために、刑務官以外の法務省職員も勤務しています。
それが、法務教官や矯正医官といった特別な職員です。これらの職員は、給料や待遇が刑務官よりも高いのが特徴です。
法務教官
犯罪を犯した少年たちは、保護処分という処罰を受けたのちに少年院に送られます。懲役や禁錮処分を受けた少年は、16歳まで少年院に収容することが法律で認められています。
この少年院や少年鑑別所などに勤務する専門職員を法務教官と呼びます。幅広い視野と専門的な知識をもって、少年たちのきめ細かい指導・教育を行うことが任務です。
また、刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)に勤務することもあり、その場合は性犯罪や薬物依存などに関わる指導のほか、就労支援指導や教科指導等も業務となっています。
少年院は刑務所と違い、罰を与えるために強制労働をさせる施設ではありません。
罪を犯した少年たちには矯正教育を受ける権利があり、少年院の矯正教育は、在院中の少年を社会生活に適応させることを目的として、生活指導、教科(義務教育に必要な教科、必要に応じて中等教育及び高等教育に準ずる教科)、職業補導、訓練、医療を施すものとなっています。
少年院は基本的に男女別に収容されており、医療少年院以外のすべての少年院がこの方針に則っています。
初等少年院は、心身ともに健康でおおむね12歳以上16歳未満の者を収容します。中等少年院は、心身ともに健康でおおむね16歳以上20歳未満の者を対象としています。
特別少年院では、凶悪犯罪を犯した16歳以上23歳未満の者を収容し、16歳未満の受刑者も対象としています。
医療少年院は、12歳以上26歳未満で心や体に重大な病を抱える者が収容されます。現在、関東(東京都府中市)、神奈川(神奈川県相模原市)、宮川(三重県伊勢市)、京都(京都府宇治市)の4か所に設置されています。
少年院には比較的軽い罪を犯した少年が送られますが、凶悪な場合は少年刑務所に収監されます。
少年院が更生と保護を目的とする施設であるのに対し、少年刑務所は一般の刑務所とほぼ変わりなく、懲罰的性質が強くなっています。
職員も少年院では法務教官ですが、少年刑務所では刑務官が主体となっています。
なお、少年刑務所には少年だけでなく成人の受刑者も収容されています。函館少年刑務所では、職業教育訓練の一環として、実習船「少年北海丸」を用いた訓練も行われています。
矯正医官
刑務所などの矯正施設で収容者を診療する医師は、法務省の「矯正医官」と呼ばれる国家公務員です。受刑者への診療や治療が日常業務となっていますが、「保護房に収容される受刑者が何日耐えられるか」を医師の視点から見極め、刑務官に助言を行うことも業務の一部となっています。
刑務所で問題行動を起こした受刑者、あるいは働きたくないからとわざと問題を起こす者は、保護房におよそ1週間程度送られることがあります。その際、矯正医官が受刑者の身体・精神状態を診断し、何日程度の保護房収容が妥当かを判断します。
法務省では矯正医官の定員を332人としていますが、2013年4月時点では260人しかおらず、2割以上の欠員が発生している状況でした。
その原因は、やはり民間の医師に比べて給料が安いことです。
たとえば、50歳の医師の場合、民間では平均月給100万円以上が一般的ですが、矯正医官では平均月給80万円程度とのことで、20万円の差は大きく、医大の学費ローンを早く返済したい医師にとっては、待遇がネックになっています。
とはいえ、法務省では医師を積極的に募集しており、その条件は好待遇です。
国家公務員でありながらフレックスタイムが導入されており、外部の医療機関との兼業も可能です。
さらに、夜間や休日の当直もありません。医師としては魅力的な職場であると言えるでしょう。
医療刑務所
精神的または身体的に疾患を抱える受刑者を収容する施設として、法務省は専用の医療刑務所を全国に4か所設置しています。
ここでは、高齢で介護を要する受刑者、重病の受刑者、覚醒剤中毒の受刑者などが入所しています。警察官や刑務官の間では、覚醒剤を一度使用するとやめられない人が多いと知られており、再犯の可能性も高いと考えられています。
医療刑務所では、矯正医官が対応できない場合には、外部の医療機関へ搬送されることもあるため、各施設には独自の救急車が配備されています。
たとえば、精神障害者を収容する八王子医療刑務所では、「法務省」と記載された独自の救急車が運用されています。
PFI方式の「社会復帰促進センター」
近年では、PFI(Private Finance Initiative)方式により、民間企業が刑務所の業務の一部を担う「社会復帰促進センター」が各地に設置されています。
ただし、完全な民間運営ではなく、官民共同の施設であり、「刑務所」という名称は使用されていません。
現在、全国には美祢(山口県)、島根、喜連川(栃木県)、播磨(兵庫県)の4か所が稼働しています。
たとえば、美祢社会復帰促進センターでは、国との20年間にわたる517億円の契約のもと、警備会社と出版社が共同出資し、給食や巡回、職業訓練を民間が担っています。
ただし、公権力の行使が必要な場面では、公務員である刑務官が対応しています。
このセンターの特徴は、初犯や軽微な罪の受刑者のみを対象とし、規則も比較的ゆるやかである点です。
建物の外周もコンクリートの壁ではなくフェンスで囲まれており、95%以上が個室となっています。とはいえ、受刑者は一般の刑務所と同様に、髪型の自由はなく、坊主刈りに近い頭髪が義務づけられています。
なお、民間の警備員(たとえばセコム)は施設管理権を持つにとどまり、受刑者に対する公権力の行使はできません。正当防衛など、個人に認められる範囲を超える行為は許されていません。
刑務所を題材にした作品
刑務所を舞台にした作品の中には、作者自身が元受刑者であるという背景を持つものもあり、単なるフィクションではないリアリティが垣間見えることがあります。
中でも、2002年に公開された映画「刑務所の中」は話題となりました。原作は花輪和一氏による同名漫画で、実際に収監された経験をもとに描かれた実録作品です。
作中では、とくに食事の描写が詳細であり、「刑務所の食事は意外に良い」「食べてみたいが、さすがに入るわけにはいかない」といった反響もありました。
劇中では『北海道日高刑務所』という架空の施設が登場しますが、作者が実際に収容されていたのは函館少年院であり、同院では成人の収容者もいます。
作品内では、優良受刑者のみが参加できる2級受刑者集会(映画鑑賞会)が描かれており、映画『キッズリターン』を観ながら、受刑者たちが「甘シャリ」(甘い菓子)こと『アルフォート』を無言で口に運び、コーラで流し込むという、印象的なシーンが展開されます。
この菓子は普段は祝日か正月、あるいは受刑者集会などの特別な場でなければ提供されないもので、受刑者たちにとっては貴重なひと時です。
映画が終了すれば、すべては元どおりに戻り、包装や空き缶はその場で回収され、感想を口にすることも許されず、受刑者たちは2列縦隊で雑居房に戻されます。
中には、刑務官への当てつけのように空き缶を乱暴に投げる者もおり、その際の刑務官の鋭い視線など、演出も非常に細かく描かれています。
この映画を観終わって改めて気がついたのですが、本作には冒頭のミリタリーキャンプ(コンバットゲーム)シーンを含め、女性が一人も登場しません。男性のみが収監される男子刑務所が舞台ですので、それも当然といえば当然のことなのかもしれません。
皆さんもこの映画をご覧になる際は、アルフォートとコーラをご用意されると良いかもしれません。
刑務所が舞台とはいえ、現実のような深刻なイジメや暴力などの描写は控えめで、怖いと感じられる場面といえば、受刑者たちが青空の下で淡々と自らの罪を語るシーンや、それに続いて刑務官が怒鳴り散らす場面くらいでしょうか。
特に印象的だったのは、老受刑者がクロスワード雑誌に直接答えを書き込んでしまい、不正行為として刑務官に厳しく叱責されて、数名の刑務官によって独房に連行されていく場面です。あまりに無慈悲で、胸が締めつけられるような思いがしました。
それでも全体を通してみると、花輪氏を演じた山崎努さんをはじめ、同房の受刑者たちによる味わい深い演技や、どこか仄々とした音楽の効果もあり、刑務所を舞台にしていながらも不思議と安穏とした雰囲気のある作品となっています。むしろ、ブラック企業を描いた映画の方が、よほど凄惨だったりするのかもしれませんね。
なお、彼が収監される原因となったコルト・ガバメントの入手や、修理にまつわるエピソードは、『刑務所の前』にて描かれています。こちらも併せてご覧になると、一層楽しめることでしょう。
刑務所と食事、いわゆる“檻メシ”といえば、土山しげる氏の『極道めし』も忘れてはなりません。土山氏は「噴飯マン」などをはじめ、食にまつわる作品を数多く手がけており、食へのこだわりが強い漫画家としても知られています。
ただし、『極道めし』は本作とはやや趣が異なります。こちらでは、ムショという極限の空間の中で、各受刑者が「美味かったメシの思い出」を語り合うのが主な題材となっています。刑務所では年に一度、正月に豪華なおせち料理が支給されるのですが、それをかけて、同室の受刑者たちがそれぞれシャバで食べた“最高の一皿”を披露し合う、という一風変わった作品です。
語り手たちは、それぞれの人生の背景とともに、こだわりの一品を語ります。そして、それを聞いた同室の仲間たちが「ごくり」と喉を鳴らした回数が多かった受刑者が勝者となる、というルールになっているのです。
もちろん、他の受刑者から食事を融通してもらうのは規則違反で、刑務官に見つかれば懲罰を受けることになります。なお、『極道めし』も映画化されていますので、こちらもあわせてチェックしてみてはいかがでしょうか。
最後に、アメリカ映画に登場する刑務所についても少し触れておきたいと思います。
壮大なスケールで描かれた映画『グリーンマイル』は、やや古い時代設定ではありますが、死刑囚と刑務官との心温まる交流が描かれており、観る者の心を静かに揺さぶる名作です。
また、シルヴェスター・スタローン主演の『ロックアップ』も印象的です。この作品は、ニュージャージー州ラーウェイにある東ジャージー州刑務所で撮影されており、本物の囚人たちがエキストラとして参加していることで話題となりました。
このように、国や時代は異なれど、刑務所を題材とした作品にはそれぞれに独自の味わいがあります。是非、観比べてみてください。