実は日本警察がMP5機関けん銃を運用し始めたのは、正式な公表よりもはるかに早く、警視庁の秘密部隊SAP(Special Armed Police)時代にさかのぼる。
1977年のダッカ日航機ハイジャック事件、そしてドイツのGSG9が手腕を見せたルフトハンザ機救出作戦を受けて、警視庁は水面下で「対ハイジャック部隊」を創設した。
これは後のSATの前身であり、「SAP」や「零中隊」と非公式な名称で呼ばれ、その存在は長く非公開とされた。
今回は日本警察が特殊部隊SAP(Special Armed Police)時代から現在のSAT(特殊急襲部隊)に至るまで、H&K MP5機関けん銃を導入・運用してきた背景を踏まえた考察をしたい。

―日本警察と機関けん銃の“沈黙の歴史”―
ドイツ製のH&K MP5機関けん銃。ドイツ製のこの火器は、高い命中精度とコンパクトな設計、加えて屋内戦向けの取り回しやすさから、突入任務に適していた。
特にサプレッサー内蔵のMP5SD5/6は、夜間の羽田空港で行われていた極秘訓練にも最適であり、非公然特殊部隊SAPの「秘匿装備」だった。
なお、当時のSAPでは武器を除く装備購入は隊員の自己負担に頼っていたという証言も残る。

その後、1995年の全日空857便ハイジャック事件でSAPが事実上の初出動を果たし、翌96年にSATとして公式化される。
ここでようやくMP5の存在も暗に認められる形となり、フィクション作品ではSATの装備として描かれることも多くなった。
2002年、日本警察によるMP5導入の公表
ただし、警察庁が国民に正式にSAT装備品としてのMP5(いわゆる機関けん銃)に関して、秘匿を解除し、不特定多数の国民に公知したのは2002年のSAT訓練動画公開および平成14年版警察白書(2002年)が初めてである。

外国の政府機関が配備する3点バースト付きのMP5短機関銃(機関けん銃)の実物。 photo by Rizuan
同白書では、警察庁自らが「信頼性の高い装備品」として次のように記述している。
この機関けん銃は、銃の性能に対する信頼性、警備対象となる重要施設周辺の環境、外国警察における導入実績等を考慮し、上記のような任務に当たる銃器対策部隊員等が所持するのにふさわしい銃種として選定したものであり、国際テロ情勢等を踏まえながら、的確な運用を行うこととしている。
出典および引用元 警察庁公式サイト『平成14年 警察白書:(2)テロ対処部隊の活動』:https://www.npa.go.jp/hakusyo/h14/h140202.html
つまり、日本警察によるMP5の導入意義は、高い信頼性と世界的な実績、国内施設での使用適合性という理由に他ならない。
まるで2000年以降に突然導入されたかのような文面だが、実はMP5はSAP創設期から今日のSATに至るまで、日本警察の対テロ部隊を40年以上にわたり、国民に秘匿しつつ運用されていた事実がある。

そして、警察白書がベタ褒めしたのは「2002年の情勢と技術水準」時点においてであり、2020年代の治安と火器事情にMP5は必ずしも適合しているとは言えないというのが結論だ。
それはなぜなのか。詳しく見ていこう。
MP5は警察向けの理想的な装備である
MP5(Heckler & Koch製の9mm短機関銃)は、一般的に反動が比較的軽い部類に属する火器である。
これは、使用弾薬が9×19mmパラベラム弾であること、そしてローラーロッキング方式の閉鎖機構によって、撃発時の反動がスムーズに制御されている構造に起因している。多くの射手が「撃ちやすさ」や「コントロールのしやすさ」を評価しており、法執行機関や対テロ部隊などで広く採用されてきた理由の一つでもある。

画像の出典 警視庁、射撃競技大会開催=機動隊対抗、早撃ちなど7種目で腕前披露 時事通信トレンドニュース
また、MP5の設計には「誰にでも一定の訓練で習熟できる」という汎用性の高さも理想的だ。 体格や性別による影響を比較的受けにくい点が評価されている。警視庁射撃競技大会では銃対の女性警察官がMP5を扱う場面が確認されている。
MP5は確かに、都市型のテロやハイジャック、立てこもりといった事案には理想的であり、SATや各地の銃器対策部隊で今なお第一線の装備品である。
MP5はもう時代遅れか?
しかし、2007年の長久手町事件でSAT隊員が殉職したことを契機に、防弾装備の限界、そして現代的火力への対応不足といった問題が表面化するようになる。
世界的には既に、9mm弾の貫通力不足が指摘されており、MP5はHK416やSIG MCXといったライフル弾対応の短小カービンに置き換えられつつあり、防弾装備が普及した現代の脅威に対しては火力面で不安が残る。
にもかかわらず、日本ではMP5がなお主力であり続けている。2015年には銃器対策部隊への自動小銃配備の計画も公表されたが、いまだに訓練では出てこない。
これは更新に際して、装備そのものの性能以上に制度・予算・世論の壁が立ちはだかっているからだ。新型火器の導入には武器等製造法や予算措置の問題が絡み、政治的には警察の「軍事化」を警戒する声も根強い。
現場が必要としても、中央の判断や制度が追いつかず、結果としてMP5は「変えられない標準装備」として居座っているのが実情である。
SAPの誕生と“見えざる武器”MP5
1977年、ダッカ日航機ハイジャック事件と、その直後にドイツのGSG9が成功させたルフトハンザ機救出作戦は、日本警察に大きな衝撃を与えた。
当時、警視庁はこれに倣い、非公開部隊SAP(Special Armed Police)を立ち上げた。
このSAPにおいて、当時、技術指導を受けていた西ドイツ国境警備隊の特殊部隊「GSG9」経由で秘密裏に調達されたのがH&K MP5であった。
公式には存在しない部隊に、予算も法的裏付けもないまま、当時世界最高水準のサブマシンガンが日本警察に届けられたという経緯は、異様ですらある。
軍用弾への移行と「警察の軍事化」の国民世論 — 国境離島警備隊への自動小銃配備をめぐって
世界ではすでに、MP5は第一線から退役が進行中である。ドイツ連邦警察、フランス国家憲兵隊GIGN、米国のローカル警察機関のSWATやFBI HRTなど連邦法執行機関でも、HK416、SIG MCXなどカービンが主流である。また、パトカーに「パトロールライフル」を搭載するという新たな運用スタイルも定着している。

しかし、日本では以下の理由が懸念されている。
-
軍用弾(5.56mm等)への移行は、「警察の軍事化批判」を招きやすい
🔻補足:事実として確認できる点
-
SAP時代からMP5を装備していたとされる(出典:元警察特殊部隊員の著書、訓練写真など)
-
警察庁白書では「機関けん銃」として平成14年に初めて明記
-
MP5は現在もSATや銃器対策部隊で運用されているが、銃対や国境離島警備隊では「自動小銃」が導入されたという報道もある
MP5はなぜ評価されたのか?
MP5(Heckler & Koch製)は1960年代に西ドイツで開発され、世界各国の特殊部隊や法執行機関で採用されてきたサブマシンガン(機関けん銃)である。
▶ MP5の優れた点
-
コンパクトでありながら拳銃弾による高精度連射が可能
-
GSG9、SASなど欧米の精鋭が採用し、実戦で成果
-
空港やビルなど狭所・屋内戦に最適
-
無音性(MP5SD)が突入作戦に不可欠
-
使用弾薬:9mmパラベラム弾(拳銃弾)
-
特徴:低反動、精度良好、連射時の制御性に優れる
-
静粛性:MP5SD型ではサプレッサー標準仕様で極めて静音性が高い
-
運用性:屋内・CQB(近接戦闘)に最適化
SATや銃器対策部隊での採用は、人質救出や建物内突入など、まさに“都市型治安任務”にマッチしていた。

しかし――今や「時代遅れ」なのか?
採用から20年以上が経ち、いくつかの「MP5限界論」も聞かれるようになった。
世界的には、MP5に代わってHK416やSIG MCXなどの小口径カービンが近接戦用火器として主流となりつつある。日本の警察部隊では、現時点でそれらの装備が導入されたという公的な発表や信頼性の高い報道は確認されておらず、MP5が依然として主力火器として用いられている。
しかし、近年の脅威環境を考慮すれば、今後の装備更新が必要になるという指摘もある。
✅ 1. 拳銃弾の貫通力不足
アメリカにおいては、敵対勢力が防弾ベストを着用する例が増え、9mm弾では致命傷になりにくい状況が90年台から警察の脅威となっている。これに対し、米国警察機関ではAR-15系(5.56mm)カービンへの移行が進んでいる。
✅ 2. 命中精度とアタッチメント対応
MP5は設計が古く、最新のドットサイト・レーザー・ライト等の拡張性に限界がある。現在ではピカティニーレールが標準化され、HK416やSIG MCXなどモジュール性に優れたプラットフォームが主流。
✅ 3. 武装被疑者への対応
長久手町事件(2007年)のように、拳銃でさえSAT隊員が被弾・殉職する例が生じている。状況によっては拳銃弾では火力不足となる可能性が現実化している。
◆ 日本警察は更新を検討していないのか?
現時点で公表されている装備更新の兆候は限られている。ただし、以下のような動きは確認されている:
-
SATでは89式小銃(5.56mm)を一部導入していると見られており、火力強化と貫通力の向上が模索されている。
-
銃器対策部隊で自動小銃の配備を決めたとする報道が2015年にあった(ただし、2025年現在まで一度も公開されていない)。
しかし、一般公開された文書や装備からは、MP5は今なお多くの場面で「主力装備」として残っている。
結論:MP5は“役目を終えた”のか?
警察庁も認めている通り、MP5は世界的に見ても優れた装備品であり、2000年台初頭の制式導入当初は日本の特殊部隊SATの要件に極めて適していた。
ただし、それは任務と対象が限定された場合に限る。
-
人質救出・建物内突入・市街地戦術では有効だが、防弾装備の犯人・広域対応・車両襲撃には火力不足も否めない。
長久手事件や、自衛隊員による小銃乱射射殺事件など、国内の銃器犯罪の変化により、拳銃弾を使用する『機関けん銃』で制圧するリスクが顕在化してきた。
それでもなお、MP5が使われ続ける背景には、日本警察における装備更新が、法的・政治的、さらには国民世論といった制約が重なり、現場が求める性能と制度の整備とが一致していない現状がある。
-
日本独特の「制度が追認する文化」
-
公安上の装備非公開主義
-
装備更新が予算・政治・国民感情のはざまにある現実
が複雑に絡み合っているのだ。
MP5は確かに優れた銃であるが、先進国と比較しても、すでに「万能の装備」としての立場は揺らいでいるのは事実である。
新たな脅威環境に適応し、より柔軟かつ透明な装備更新体制を構築しなければ、警察の対テロ能力は制度によって足を引っ張られ続けることになる。その意味で、MP5の役割を再評価することは、単なる銃器の問題ではなく、日本の治安体制そのものを問い直す作業でもある。
短機関銃の“運用限界”を見極めたうえで、次世代火器への移行と用途分担を図るべき時期に、すでに来ているのかもしれない。

参考文献一覧
-
「【訓練映像】警視庁、初の実弾射撃訓練公開=サブマシンガン連射で犯人制圧」
MP5を携行し展開する実弾訓練の様子が確認できる
YouTube(時事通信トレンドニュース)
https://www.youtube.com/watch?v=INjzmHi6xnM -
「特殊部隊SATと銃器をクローズアップ 」
MP5の構造や反動の軽さについて専門的に解説
アームズマガジンWEB
https://armsweb.jp/report/5294.html - 「The Range 702 – MP5 Features, Specs, and History」
サバイバルガンレンジによる歴史・技術・使用実績の紹介記事。詳細かつユーザー目線での解析あり。
https://www.therange702.com/blog/mp5-gun-spotlight/
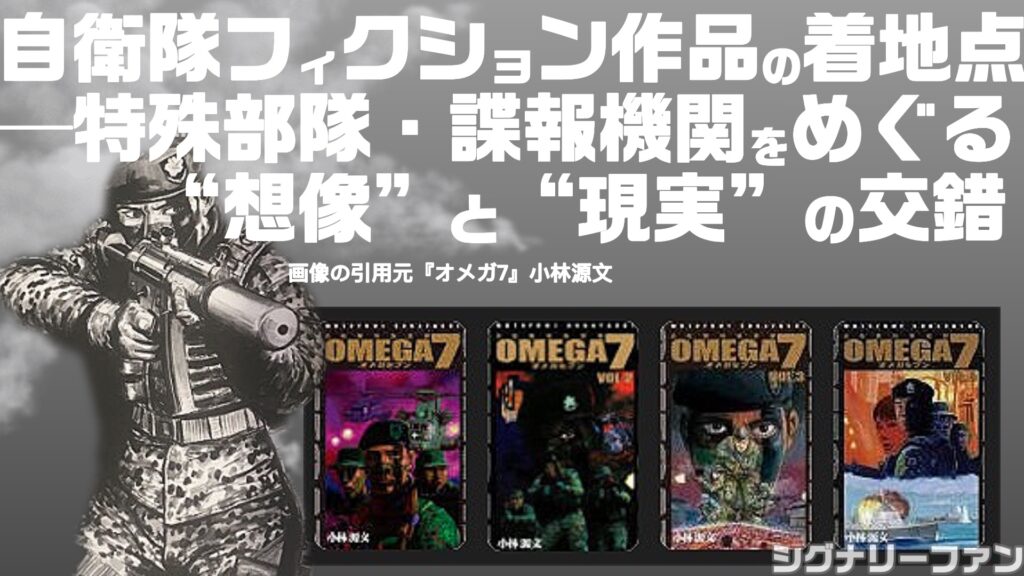
他の関連記事もぜひご覧ください。











































































































