アメリカで運用されている「連邦航空保安官(Federal Air Marshal:FAM)」の制度・任務・運用実態・課題を、事実に即して中立に解説します。
Federal Air Marshal Service(連邦航空保安官隊)の成立と変遷


航空先進国アメリカでは、1960年代からすでに航空機ハイジャックへの対策として、武装した連邦職員を機内に乗せる「スカイマーシャル制度」が試験導入されました。
1961年、キューバへのハイジャック事件が相次いだことを受け、連邦航空局(FAA)管轄下で武装保安官を搭乗させる運用が始まったのが前身です。
その後、2001年9月11日の同時多発テロ事件を契機に制度が再編されます。武器も持たない乗務員・乗客が全く対応できなかったことを教訓に、TSAが創設され、FAMもその傘下で再編強化されました。
航空保安体制を一元化するため、同年11月に運輸保安庁(Transportation Security Administration:TSA)が新設され、連邦航空保安官(局)(Federal Air Marshal Service:FAMS)はその傘下へと移管。2002年までに正式な法執行部門として統合されました。
テロ直後には空軍や連邦捜査局(FBI)出身者が大量採用され、FAMの人員は急速に増強されました。
現在では、TSAの「Law Enforcement/Federal Air Marshal Service(LE/FAMS)」として、航空機内の警備・ハイジャック防止・テロ抑止を担っています。
なお、「スカイマーシャル(Sky Marshal)」という言葉は1970年代の呼称であり、現在の正式な制度名は「Federal Air Marshal Program」です。
連邦航空保安官と9・11テロ事件
「空を守る警察官」誕生の背景
空の旅がテロリストの標的になり得ることを、世界が決定的に悟ったのは2001年9月11日でした。
ハイジャック犯が大型旅客機のフライトデッキに侵入し、機体そのものをミサイルのように操ってニューヨークの世界貿易センタービルへ突入させたあの同時多発テロ事件は、航空安全の概念を根底から変えた出来事でした。
当時、航空機がハイジャックされた場合の各国の基本的な対応は、あくまで「地上での奪還作戦」でした。
日本の警察の特殊部隊(SAT)も訓練や戦術面で参考にしているドイツの対テロ特殊部隊GSG-9は、1977年に発生したルフトハンザ航空181便ハイジャック事件での突入作戦により、世界的にその名を知らしめました。
当時は給油や整備のタイミングを狙って特殊部隊が突入したり、滑走路上で狙撃手が対物ライフルで機内の犯人を狙うといった対応が主流で、飛行中の機体内で犯行を未然に防ぐ体制はほとんど存在しなかったのです。

9・11事件は、その「発生後の対処」という従来の考え方を完全に過去のものにしました。
旅客機が武器として利用されるという発想は、テロ対策の常識を覆し、米国は直ちに航空保安体制を抜本的に見直します。
そこで再編によって人員を大幅に増員させたのが、連邦航空保安官(Federal Air Marshal:FAM)制度でした。
航空保安当局は、「テロリストに手を差し伸べることはない」として、具体的な人員数や搭乗便数などの詳細をメディアには公開していません。
しかしながら、Federal Air Marshal Service(FAMS)は、2001年の同時多発テロ事件を契機に、機内で乗客に紛れて任務にあたる「連邦航空保安官」がごく少数(50人未満)だったところから、翌年以降に「数千人規模」へと急速に拡大したと、米国政府監査局(Government Accountability Office:GAO GovInfo)の報告書が示しています。
とはいえ、FAMSが各便に搭乗している割合は、2000年代半ばでも1%程度あるいはそれを下回るとする分析もあり、米国内を運航する1日あたり2万件以上の定期便全てに配備されているわけではありません。
定期便数については2005年時点で「1日あたり約25,000便」との報告もあり、すべての便に保安官を配置するのは現実的に非常に困難な状況です。
2025年現在、アメリカでは政府期間の閉鎖が相次いでおり、FAMSも影響を受けています。
連邦航空保安官の普段の任務
連邦航空保安官(Federal Air Marshal、以下FAM)は武装した法執行官であり、一般の乗客に紛れて搭乗し、テロやハイジャックを水際で防ぐことを任務とする武装警察官です。
民間航空機のキャビンという閉鎖空間で、犯人を即座に制圧し、他の乗客を守る訓練を受けています。
連邦航空保安官(FAM)は、見た目は普通のビジネスマンですが、実際には拳銃を携行し、民間航空機の機内で潜在的な脅威を監視しています。
FAMの主たる任務は以下のとおりです。
-
商用旅客機内に秘密裏に搭乗し、不審者の監視とハイジャック対処に備える
-
機内での暴力行為、乗員への妨害行為(unruly passenger)に即応
-
国際線・国内線を問わず、ハイリスクな便を選定して重点搭乗
-
空港内の監視活動や、航空会社との連携訓練にも参加
公式説明によれば、彼らの主な任務は「航空輸送システムの保護」つまり、ハイジャックやテロ行為、暴力的行動など、航空機の安全を脅かすあらゆる事案に即応するのが任務です。
そのため、搭乗時は身分を隠し、一般客のふりをして行動するのが鉄則です。機内で不審な動きを察知すれば、数秒以内に制圧に移ります。
拳銃は9mmオート。発砲は「機体を損傷させず、短距離で停止力を発揮する弾薬」を使用するとしています。類推すると、これは「フランジブル弾」であると見られます。

TSAによると、FAMは国内線・国際線問わず「リスク評価と情報分析に基づいて」配備され、どの便に誰が乗っているかは完全に機密扱いです。
一方で、彼らは空だけでなく、「Visible Intermodal Prevention and Response(VIPR)」という対テロ支援プログラムを通じ、“見える抑止力”として鉄道や港湾、地下鉄などの公共交通でも活動しています。
(出典:TSA公式サイト、jobs.tsa.gov、GAO報告書 GAO-04-242)
つまり・・・
-
すべての便に搭乗しているわけではない。
-
テロリズムや犯罪捜査の情報を元に、“高リスクと判断された便”に選定搭乗される。
-
搭乗の有無や配備状況は機密情報扱いであり、原則非公開。
という任務になっています。
武装と訓練
FAMはTSA配下ながら、連邦法執行官としての逮捕権と武装権限を持っており、その訓練は非常に厳しいのが実情です。
FAMは制服を着用せず、一般客を装い、拳銃と法執行官のバッジを密かに携行して搭乗します。
-
装備
-
主にSIG Sauer P229、P239またはグロック19、グロック26を秘匿携行。
- 弾丸は貫通力の高い通常弾頭ではなく、砕けやすいグレイザー・セーフティ・スラッグ(フランジブル弾)を装填。なお、日本の警察でも同様の措置を行っている。
-
隠し持てるサイズのASPバトン
-
-
訓練と実運用
-
近距離射撃や格闘術、心理判断(不審者の観察)、機内構造への熟知
-
機内における「最小被害での制圧」が重視される
- 匿名の保安官によると、彼らは「攻撃者を撃って止める」ように訓練されており、通常は体の最も大きな部分(胸部)を撃ち、次に頭部を撃って神経系を無力化する。
-
■ 運用上の課題と批判
● 運用の非効率性
-
膨大な数の便に対し、FAMの人数は限られており、「網羅的なカバー」は困難。
-
乗客に紛れるための負担(過度の飛行勤務、心理的ストレス)が蓄積。
● テロ対策効果への疑問
-
ハイジャックが主な想定であるが、現代のテロは無人機や爆発物にシフト。
-
「最前線の抑止力」としての象徴的存在にとどまっている面もある。
● 組織運営と士気の低下
-
過重勤務・長時間の不規則フライトにより、近年はFAMの離職率が上昇傾向。
-
予算削減により、搭乗率も縮小しているとされる(非公式情報)。
■ 近年の動向
-
2020年以降、TSAは一部FAMを空港地上勤務にも転用(COVID-19対策やセキュリティ対応)
-
機内での“迷惑乗客(air rage)”対応に重点を移す方向性も強まっている
-
ドローン対処やサイバー面の航空セキュリティなど、「新たな任務分野」にも模索が始まっている
旅客機のパイロットに銃を持たせる「Federal Flight Deck Officer Program」とは
アメリカでは、民間旅客機または貨物機のフライトデッキを保護する一手段として、運航乗務員(主にパイロット)を対象に武装を許可する制度、FFDO(Federal Flight Deck Officer Program)があります。
2002年11月に成立した「Arming Pilots Against Terrorism Act」によって法制度化され、翌2003年ごろから訓練と任命が始まりました。
参加資格にはアメリカ市民であること、FAAのパイロット証明・医学証明を保持していることなどがあり、選抜された乗務員はフライトデッキ保護のために訓練を受け、TSAの定める基準に沿って拳銃携帯が認められ、「連邦法執行官(Federal Law Enforcement Officer)」としての地位を取得します。
任務範囲は主に飛行中の機体フライトデッキの防御で、武器使用などの対応基準も法律およびTSA指針で定められています。
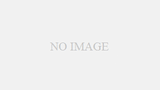
日本や諸外国では?
世界的に見ると現在、米国以外の多くの国でも、スカイマーシャル(Sky Marshal)と呼ばれる同様の制度が導入されています。
ヨーロッパでは、イギリス、ドイツ、フランス、オーストリアなどがFAM類似の制度を導入しています。
-
イギリス:Civil Aviation Authority(CAA)傘下の「Air Security Officer」制度があり、警察官が旅客機に搭乗して警戒します。配備は国際線中心で、全便への配置はなし。
-
ドイツ:Federal Police(Bundespolizei)が「Luftsicherheitsbeamt*innen」を配置。特定便への搭乗が中心で、任務内容はテロ抑止と事後対応。
-
フランス:Gendarmerie nationaleの航空部隊が一部国際便に搭乗。武装搭乗は極めて限定的。
一方日本では、国土交通省と警察庁が航空保安の責任を分担していますが、2004年以降、一部の国際線で「航空機警乗警察官(スカイマーシャル)」が搭乗し、警戒に当たる体制が整備されました。

米国のFAMのように大量に配置されるわけではありません。
たとえば、羽田・成田発の特定の国際線では、警察官が「乗客に紛れて」搭乗することがありますが、その人数は限定的で、航空便全体に対する割合は非常に低く、配備の具体的な便数や人数は公表されていません
このように、ほかの国々も、米国FAMのようにすべての便に武装要員を配置する体制は現実的に不可能とされています。多くの場合、危険性の高い路線や重要便、国際線中心に限定して運用しています。
まとめ
連邦航空保安官(FAM)は、航空機という特殊な密閉空間での不測事態に備える最後の砦として運用されています。
しかし、その制度は9.11以降に急拡大した反面、任務の非効率性や現代の脅威との乖離、組織の持続性に課題を抱えています。
今後、航空機内の安全確保が「武装した人員の常駐」から「テクノロジー・インテリジェンスを駆使した予防」に軸足を移す中で、FAMの制度もまた転換点を迎えているといえそうです。
連邦制が規定するアメリカの法執行構造― 州政府と連邦政府の「二重構造」が生む捜査権限の境界線とは
▶︎ https://amateurmusenshikaku.com/security/us_renpou/
関連機関別 解説記事リンク一覧
-
FBI(連邦捜査局)
▶︎ https://amateurmusenshikaku.com/security/fbi/ -
USマーシャル(連邦保安官局)
▶︎ https://amateurmusenshikaku.com/security/united-states-marshals-service/ -
DEA(麻薬取締局)
▶︎ https://amateurmusenshikaku.com/security/dea/ -
ATF(アルコール・タバコ・火器および爆発物取締局)
▶︎ https://amateurmusenshikaku.com/security/bureau-of-alcohol-tobacco-firearms-and-explosives/ -
ICE(移民・関税執行局)
▶︎ https://amateurmusenshikaku.com/security/ice/
















































































































