刑事ドラマや映画には古くから警察無線のシーンが数多く登場してきました。
ときには実際に使われる通話コードを交えて演出されることもあり、警察密着番組などで目が肥えた視聴者の前で、いかにリアルに交信シーンを演じられるかが役者の腕の見せ所ともなっています。

警察無線の描写が登場する作品の中でも、1982年に公開された映画『野獣刑事』は、警察無線マニアの間で今も「伝説的作品」です。
特に注目されるのは、劇中のカーチェイスシーンに登場する大阪府警本部の通信指令です。
ここで用いられている通話コード、緊急配備(いわゆる「キンパイ」)の発令内容、そして淡々とした口調での読み上げは異常なほどのリアリティがあり、実際の警察無線を聴き込んでいなければ再現が難しい水準と言えます。
製作スタッフやナレーターは、事前に警察無線を傍受し、そのやりとりを参考にした可能性が高いと推察されています。
当時はアナログ方式の警察無線が使用されており、受信機があれば誰でも容易に聴取できる時代でした。いわば「警察無線傍受ブーム」とも呼べる現象が起きていたのです。
このブームを牽引したのが、1980年に創刊された月刊誌『ラジオライフ』でした。
発行元の三才ブックスは、創刊号(1980年6月号)から「誰が聞いてもいい警察無線」といった挑戦的なキャッチコピーを掲げ、全国の警察無線の周波数や通信系統(基幹系・署活系)、傍受方法までを網羅的に紹介しました。
この特集は社会的な反響を呼び、警察無線傍受という趣味が広く知られるきっかけとなりました。
実際、毎日新聞も当時この現象を報道しています。記事によれば、警察庁や警視庁は『ラジオライフ』の特集に対し不快感を示し、当時の郵政省電波監理局に「周波数公開は電波法違反ではないか」と照会しました。
しかし、電波監理局は「違反には当たらない」との見解を示し、事実上“合法”とされたのです。
こうした背景を踏まえれば、『野獣刑事』のリアルな無線描写は、当時の「警察無線ブーム」という時代状況を反映して生まれたものと考えられます。
その後も『ラジオライフ』は、無線やBCL(放送受信)を中心に扱いながら、警察無線や警察装備の研究、交通取り締まり手法の分析、覆面パトカーの識別法、さらには婦警さん(女性警察官の旧称)の写真投稿コーナーやマニア同士の交流欄など、多様な企画を展開していきました。次第に誌面は「マニア文化」の色合いを強めていったのです。
1980年代末に警察の基幹系無線がデジタル化され、傍受が困難となった後も、『ラジオライフ』はアナログ署活系(地域署の通信)や、アナログ消防無線、自衛隊GCIなどのネタを扱い続け、1990年代末には初代デジタル無線機「MPR」の解読成功でも話題を集めました。
見ていきましょう。
本記事は、かつて運用されていたアナログ警察無線の技術的変遷や制度背景について、公開情報や専門誌の報道に基づき解説するものです。現行の警察無線はデジタル暗号化されており、暗号通信の解読は不可能かつ違法です。本記事は違法な受信や行為を助長・推奨するものではありません。電波法等の法令遵守を前提としてお読みください。
ドラマの中の警察無線の交信、実は本物が使用された事例も多かった!?

ドラマの中で聞こえてくる警察無線のやりとり。実は、その中には実際の警察無線音声が使用されたケースも存在しています。
その一例が、1989年にテレビ朝日系列で放映された刑事ドラマ『ゴリラ・警視庁捜査第8班』です。
この作品では、実際に神奈川県警本部から発信された一斉指令の無線音声が劇中に使用されていたと伝えられています。使用されたのは、当時アナログ方式だった「高速系」と呼ばれる通信系統です。
この事例は、こちらのブログ(出典:https://blog.livedoor.jp/mokei352/archives/51185147.html)で紹介されています。
同ブログによれば、当時の刑事ドラマ制作現場では「背景音として本物の警察無線録音をしばしば利用していた」とのことです。
臨場感を高める演出の一環として、実際の警察無線が録音・加工されて使用されていたと見られます。
こうした背景を踏まえれば、1982年公開の映画『野獣刑事』で描かれた極めてリアルな警察無線シーンにおいても、実際の交信音声が一部取り入れられていた可能性は十分に考えられるでしょう。
実際の警察無線の音源をドラマに使用することは電波法違反になるか

では、こうした“本物の無線音声”を映像作品で使用することは、法的に問題はないのでしょうか。
この点について、『ラジオライフ 1982年 11月号』に掲載された特集記事が参考になります。同号では「電波法はキミのもの!!──警察無線の傍受は処罰されない──」と題した企画の中で、弁護士の瀬戸英雄氏が編集部の質問に答える形で警察無線と電波法の関係を解説しています。
この中で、テレビドラマに実際の警察無線音声を使用するケースについても言及されています。
瀬戸弁護士は、仮に本物の交信を使用していたとしても、「具体的にどこの誰がどのような状況で発信した無線なのかが特定できないよう配慮されていれば問題はない」と説明しています。
仮に本物の交信をドラマの中で使っていたとしても、具体的にどこの誰がどのような状況で発信した無線を使っているのかがわからないような取り扱いがされていれば、問題はありません。
(出典:『ラジオライフ』1982年11月号「電波法はキミのもの!!──警察無線の傍受は処罰されない──」)。 弁護士 瀬戸英雄と編集部の対談より
つまり、発信者や現場が特定される恐れがなく、またプライバシーや業務の秘密に関わらない範囲であれば、電波法違反には当たらないという見解です。
この考え方は、報道番組内で警察無線の音声が紹介される場面にも適用されるとのことです
また、同特集では他にも以下のような個別のケースを取り上げています。
-
電器店の店頭で受信機から警察無線が流れている場合の違法性
-
負傷した警察官に代わって市民がパトカーの無線で救援を要請した場合の法的扱い
-
傍受した警察無線の内容を基に犯人を発見し、110番通報した場合の是非
これらの問いかけは、受信マニアとしても電波法との兼ね合いで非常に気になるケースとして、ずらり挙がっています。
実際の交信を使うことでドラマにリアリティが生まれる一方、実際に誰でも聴けた当時の警察無線だからこそ、電波法の観点から慎重な対応が求められていた――そんな時代の空気が垣間見える話題です。
なお2025年現在、ラジオライフは80年代のバックナンバーがアマゾンのKindle Unlimitedにて配信されており、すでにメンバーならば追加料金無しで全巻無料で読めます。
未会員ならばKindle Unlimitedにいますぐ入会をおすすめします。
膨大な掲載記事データが収録されており、貴重な警察関連資料がPCやスマホで閲覧可能です。
ドラマに登場する「警察無線機」——その正体は?
刑事ドラマのなかで、警察官たちが交信に使っている無線機。これらの無線機、実際にはどんな機種なのでしょうか?
実際の警察で使用されている無線機は、三菱電機やパナソニックなどが製造する警察専用機です。当然、本物の警察無線機は市販されていないため、100%入手不可能です。
また、無線機の形状や構造に関しても情報公開が限られているため、完全なレプリカを作ることはさまざまな“大人の事情”もあり、困難とされています。
そのため、多くのドラマでは市販のアマチュア無線機などを“警察無線機”として代用する手法がとられています。
たとえば、警察官募集ポスターにも登場し、長寿シリーズとして人気を集めるドラマ『相棒』では、ヤエスのアマチュア無線機「FT-8800」が警察車両の無線機として使用されていまました。
その液晶ディスプレイには、アマチュア無線の呼び出しおよび非常通信用周波数である「145MHz」が表示されており、アマチュア無線家であれば、クスッと笑えてしまう様な場面です。
また、映画『日本で一番悪いやつら』でも、北海道警察刑事部機動捜査隊の本部に置かれた警察無線機(アマチュア無線機)にアマチュアバンドの「430MHz」が表示されていたという指摘も。ここでも、市販のアマチュア機が小道具として利用されていたことがうかがえます。
テレビドラマ『警視庁機動捜査隊216』では、沢口靖子演じる機動捜査隊員が使用するハンドマイクがモトローラ製であることが確認されています。こちらも本物の警察無線機ではなく、市販の業務用無線機を応用した可能性があります。
近年では、テレビドラマ『ハコヅメ〜交番女子の逆襲〜』でも、パトカーに搭載されている車載無線機がアルインコ製のデジタル簡易無線機「DR-DPM60」であったことが、一部の無線ファンの間で話題になりました。

なお、旧デジタル警察無線機「MPR-100」のように、警察無線機のなかにも、かつては業務用モデルと同じ筐体を持った機種が存在します。
MPR-100は、同じ外見の業務用無線機が市販されていたため、ドラマや特撮作品などで“本物らしい見た目”として使われることがありました。
その代表例が、2000年に放映された『仮面ライダークウガ』です。劇中に登場する無線機が、まさにこのMPR-100と同じ筐体を用いて撮影されたものでした。
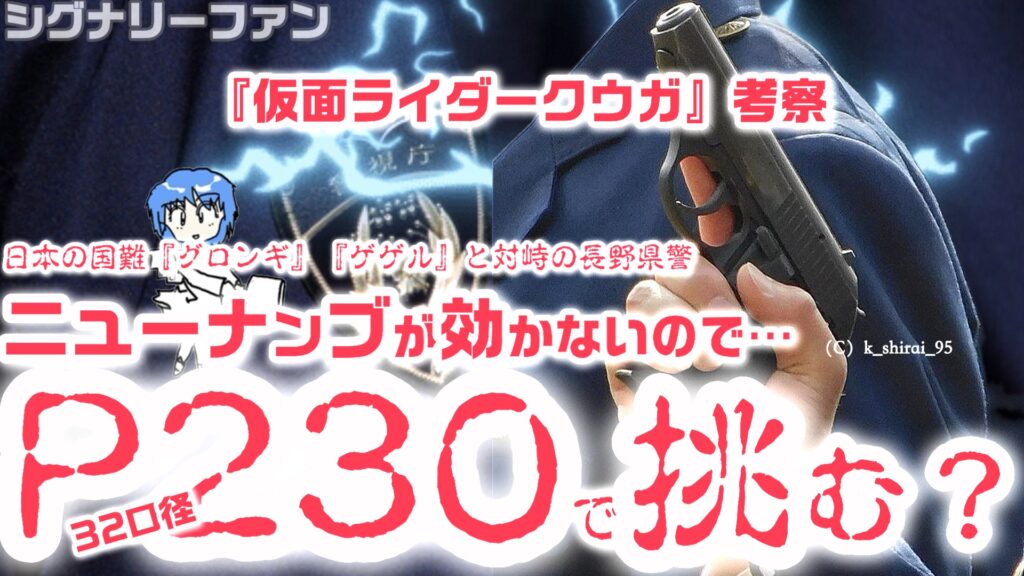
一方で、現代ドラマにおける「警察無線」の描写には、やや首をかしげたくなるような演出も散見されます。
たとえば、2014年にTBS系で放送されたドラマ『エス 最後の警官』では、高校中退の経歴をもつ犯人がアマチュア無線機を使って警察のデジタル無線を“復号”するという場面が描かれていました。
しかも、復号の結果として得られた音声には、意図的に「ザーザー」という雑音が加えられており、それがむしろ“成功の証”として演出されていました。
この、あえてノイズを混入させるという斜め上の演出に対しては、リアリティの追求というよりは演出上の誤解として、視聴者の間でも評価が分かれたようです。
また2010年から2015年までTBS系列で放送された刑事ドラマシリーズ『警視庁機動捜査隊216』でも、警察無線を巡る“懐かしい”描写が。主人公の女性機動捜査隊員が、旧知の新聞記者に向かって「あなた、ずいぶんと到着が早かったわね。警察無線でも“盗聴”してる?」と冗談めかして言うシーンがあり、このセリフもまた、今日の警察無線が完全に暗号化されたデジタル通信であり、部外者が容易に傍受できるようなものではないという現実からすれば、せっかくのリアル派ドラマを台無しにしかねない、時代錯誤とも取れる表現です。
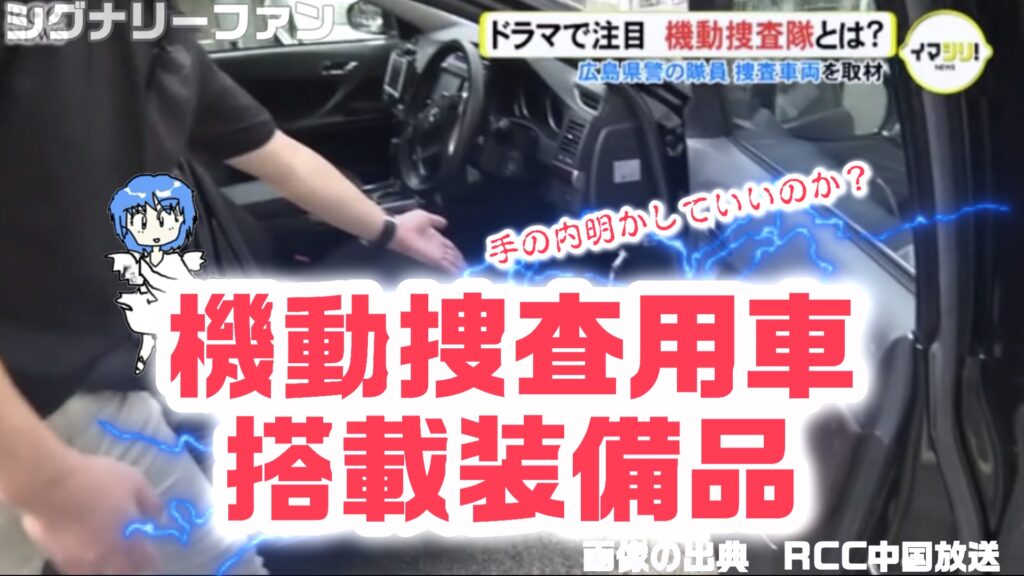
まとめ
こうして見ていくと、かつてのドラマや映画に登場した警察無線、本物の可能性が大いにあるわけです。
また、ドラマに登場する警察無線機の“正体”もさまざま。本物に似せたものもあれば、全く異なるタイプの無線機が代用されているケースも。
無線機マニアならずとも、つい気になってしまう舞台裏の“演出”の一端です。
ただし、警察無線は物語の小道具として活用されがちですが、一方で、実際の運用実態との乖離が目立つ描写には、視聴者の側にも一定の違和感が残ります。
警察を扱う映像作品においてこそ、こうしたディテールの積み重ねが、作品の信頼性を支える重要な要素となると言えそうです。
他の関連記事もぜひご覧ください。























































































































