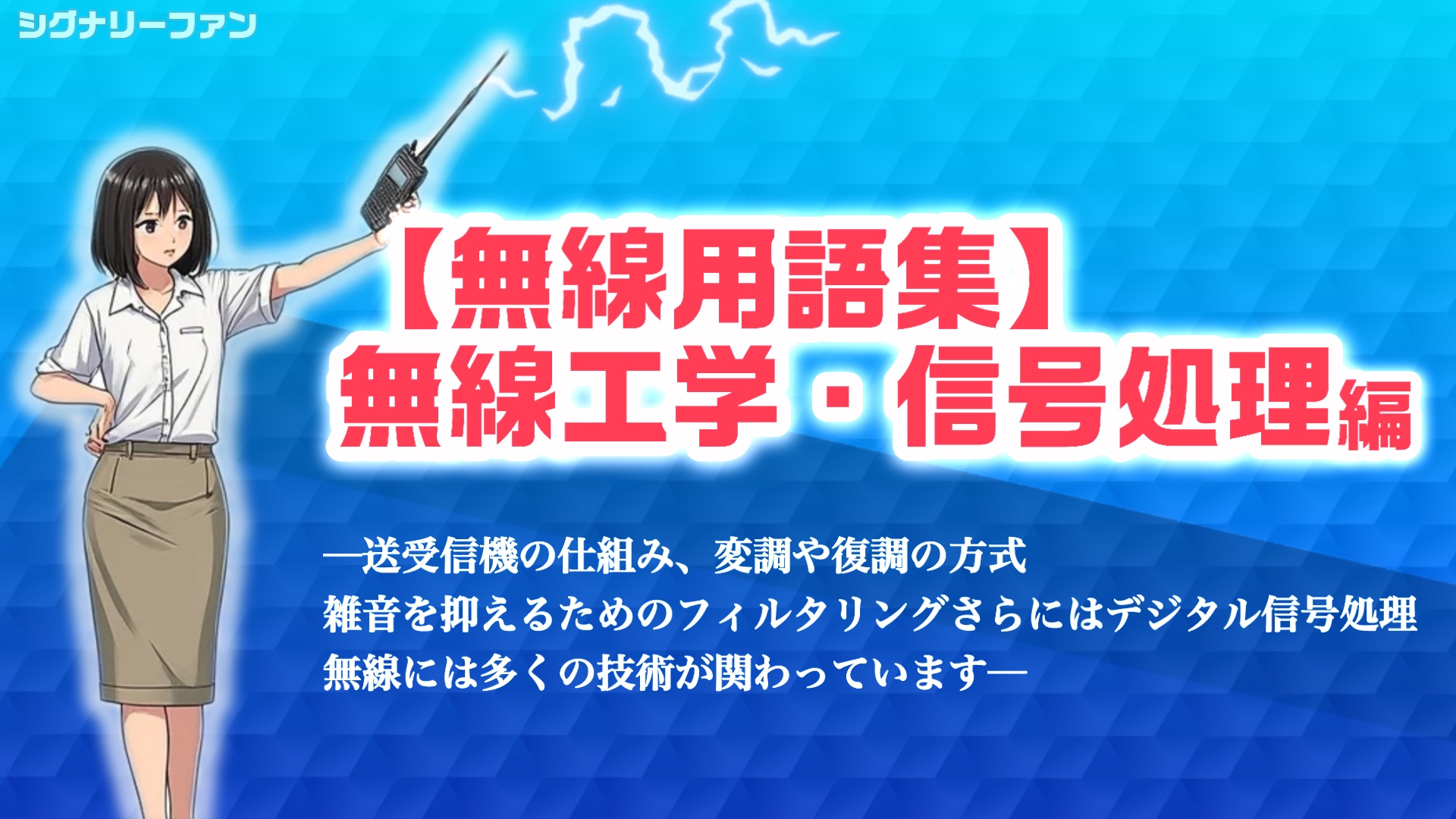はじめに
無線通信を理解するには、無線工学や信号処理の基本を押さえたいもの。
送受信機の仕組み、変調や復調の方式、雑音を抑えるためのフィルタリング、さらにはデジタル信号処理など、無線には多くの技術が関わっています。
本記事では、無線工学と信号処理に関連する用語を整理し、基礎知識を解説します。
気になる用語から各種記事にリンクで飛べますので、知識を広げながら無線ライフをより楽しんでください。
以下のリンクも併せてご参照ください。
✅無線工学・信号処理
単信式
送信と受信を同時に行えず、交互に切り替えて通信する方式をいう。この方式は、アナログの業務用無線や一部のアマチュア無線など、簡易的な通話に利用される。
たとえば、これらの無線機では、同時に送信と受信を行うことはできない。ある時点では送信、次の時点では受信、と交互に切り替えて通信を行う。
たとえば、「押して話す(PTT)」ボタンを押して送信し、話し終わったら受信に戻す方式を両局が交互に行わなければ、円滑な交信ができない。
複信式
単信式に対して複信式は、送信と受信で異なる周波数を使うduplexで、同時に双方向通信が可能である。
携帯電話や業務用無線の多くがこの方式を採用しており、会話の途切れが少なくスムーズに通信できる。
単信式は簡単で手軽、複信式は効率的で連続的な通信に向く、という違いがある。
MCA方式
MCAとは、無線ネットワークで複数の周波数チャンネルや通信経路を効率的に使う仕組みである。
単一のチャンネルでは同時に複数の通話やデータ通信を処理できないため、MCAを利用することで複数の通信を同時に行うことが可能になる。
業務用無線や緊急通信などで導入されることが多く、ネットワーク全体の通信容量を高め、干渉や混雑を抑える効果がある。
状況に応じて空きチャンネルを自動的に割り当てたり、重要な通信を優先的に処理したりできるのも特徴である。
特徴と運用
-
制御局によるチャンネル割り当て:MCA無線では、制御局が利用者に空いているチャンネルを割り当てる。全てのチャンネルが使用中の場合、利用者は順番が回ってくるまで待機することとなる。
-
通信時間の制限:1回の通信には時間制限が設けられており、通常3~5分程度である。これにより、通信の効率化と公平な利用が促進される。
-
災害時の通信手段としての強み:MCA無線は、一般の通信網が混雑してつながりにくくなる災害時においても、安定した通信を提供できる。これは、専用の無線周波数帯を使用し、制御局による管理が行われているためである。
基地局の設計に組み込まれることが多く、かつてのパーソナル無線でもMCA方式が取られていた。
また、旧・郵政省が昭和59年3月に周波数の割当て間隔を縮小し、マルチ・チャンネル・アクセス(MCA)方式を旧・アナログコードレス電話に導入した。
秘話コード
主にデジ簡、報道連絡波で使われる簡易なスクランブル技術。完全な暗号化ではないため、アルインコ DJ-X100 で簡単に秘話を解いて受信が可能。報道連絡波では、系列局で同じコードが使われる場合が多い。
トーンスケルチ
混信防止のためのスケルチ制御の仕組み。CTCSS(「Continuous Tone-Coded Squelch System(連続トーン符号化スケルチシステム)」の略称)によるスケルチ制御。
多くの受信機には「トーンスケルチ」や「DCS(デジタルコードスケルチ)」といった機能が搭載されている。
これらは、特定のサブオーディオ信号が含まれる時だけ音声を出す。単純に言えば「電波を受信しているにもかかわらず、特定の条件に合致しなければ音を出さない」という仕組みである。
表面的には音声を遮断しているだけなのだが、実際にはグループ通信を円滑に行うための重要な仕組みなのだ。
たとえば、同じ周波数を異なる会社が偶然利用していた場合を考えてみよう。
A社が業務連絡をしている最中に、近くでB社が交信を開始すれば、本来ならA社の受信機にもB社の声がそのまま混ざってしまうはずだ。
しかし、トーンスケルチを設定しておけば、A社側は自分たちのグループに割り当てたコードに合致する信号しか音声として出さないため、B社の会話は「存在しないかのように」静かに無視される。
💡 補足:この仕組みにより、同じ周波数帯を複数のグループが共用していても、不要な混信をある程度避けられるわけである。レピーターアクセスや混信防止に必須。
プリアンプ
プリアンプ(前置増幅器)は、受信機の前段に設けられる増幅回路である。
アンテナから入力された微弱な高周波信号を増幅し、後段の受信回路に十分な強度で引き渡す役割を持つ。
短波や超短波のように環境雑音や減衰が大きい周波数帯では、プリアンプの有無によって受信できる信号の明瞭度が大きく変わることがある。
ただし、増幅を強めすぎると外来ノイズや混変調まで拡大してしまうため、単純に強ければよいわけではなく、設計のバランスや利用環境が重視される。
逆トーン
トーンスケルチは、送信側が特定の低周波トーン(例:67.0Hzや88.5Hzなど)を音声に重畳し、受信側がそのトーンを検知したときだけスケルチを開く仕組み。
逆トーンはこれを「逆手」に取った方式で、トーンを検知したときにスケルチを閉じる(音が出ない) という動作になる。
つまり「指定されたトーンが含まれていない信号だけを通す」仕組みである。
逆トーンの仕組みを理解していないと「何も聞こえない壊れた受信機と誰も使ってない周波数」と勘違いされがちである。
DCS
デジタルコードスケルチ。CTCSSのデジタル版。音声ではなくビット信号で制御。業務無線や新型アマチュア機で使用。
PLトーン
Private Line Tone。モトローラ社の商標的呼び名で、CTCSSのこと。アナログFMで使われる。
セルコール
航空機に送られる識別音信号。HF帯や洋上管制などで使用される「ピーピー音」による自動選択呼出。IC-R6ではSSB非対応のため、音だけ聞こえる。
💡 補足:セルコールは警察無線でも重要指令の前に注意喚起と個別の所轄を呼び出す目的で使われていた。
空線信号
列車無線で使用される連続送信方式。通常の無線は送信時にのみ電波を発射する。
しかし、列車無線など一部の重要無線では、「現在は通話していないが、回線は正常で通信可能な状態にある」ことを知らせるため、基地局側から常に“耳障りな空線信号”として一定のトーン信号やデジタル信号を送出している。
主に名古屋、大阪のJR、東京の私鉄ではNEC方式の空線信号が使われている。
スケルチテール
送信終了時のノイズ尾。キャリアが切れた直後に出るノイズ。レピーターやモービル機で独特のクセがある。無変調、バレてないと思ってる?
給電点
給電点とは、アンテナと送信機や受信機を接続する部分を指す。ここから電気信号がアンテナに供給され、電波として空間に放射される。
逆に受信の際には、空間から受けた電波がアンテナで電気信号に変換され、給電点を通じて受信機に伝わる。
アンテナの種類によって給電点の位置は異なる。たとえばダイポールアンテナでは中央部が給電点となることが多い。
一方、ホイップアンテナや八木アンテナなどでは構造に応じた位置が設けられている。
給電点の設計はアンテナの特性に直結し、インピーダンス整合の可否や放射効率に大きな影響を及ぼす。
整合が取れていないと反射波が生じ、効率が低下するため、同軸ケーブルやマッチング回路が組み合わせて使用される場合が多い。
給電点の特性は測定器を用いて評価され、適切な設計が通信の安定性を左右する。
したがって、給電点は単なる接続箇所ではなく、アンテナシステム全体の性能を支える要となっている。
利得
利得とは、アンテナや電子回路が信号を増幅、あるいは方向付けして得られる相対的な強さを表す指標である。
アンテナ利得の場合は、特定の方向に効率的に電波を放射する能力を示し、等方性アンテナを基準にデシベル(dB)で表される。

利得が高いアンテナは、同じ送信電力でも特定方向に強い電波を届けられるため、通信距離を伸ばしたり、不要な方向への放射を抑えたりできる。
逆に利得が低いアンテナは全体に均等な放射を行うため、広範囲の通信に向く。
電子回路における利得は、入力信号に対して出力信号がどの程度大きくなるかを示す。
利得が高ければ信号は強調されるが、雑音も増幅されるため、単純に大きければ良いというものではない。
無線通信では、アンテナ利得と送信電力、受信感度などが組み合わさり、総合的な通信品質が決まる。
利得の理解は、効率的かつ安定した通信システムの設計に不可欠である。
定在波比
定在波比(SWR: Standing Wave Ratio)は、アンテナと給電線との間でどの程度効率的に電力が伝達されているかを示す指標である。
アンテナの性能を示す数値は各種あるが、SWRはその最も重要な数値の1つである。
ただし、SWRが問題になるのは受信よりも送信時である。アンテナを受信専用に使うのであれば、SWRはそれほど気にする必要は無い。
アンテナが送信機に適切に整合していない場合、供給されたエネルギーの一部が反射して戻り、給電線内で進行波と反射波が重なり合い定在波が生じる。
この反射の度合いを数値化したものが定在波比である。理想的には1:1で、これは反射がなく全てのエネルギーがアンテナから放射されている状態を意味する。
値が大きくなるほど反射が強く、送信効率が低下し、場合によっては送信機を損傷する恐れもある。
実際の運用では1.5以下が良好、2程度までが許容範囲とされることが多い。
定在波比はアンテナの設置環境や周波数によっても変動するため、測定器を用いた調整が重要となる。
つまり、アンテナの受信感度の良さは、SWRが低いほど良いことになる。
ただ、SWRが低い帯域は理論上効率良く電力を送受信できることを示しており、受信感度が比較的良くなることは多いものの、「SWRが低い=必ず感度が良い」とそのアンテナの評価を単純化するのは、正確ではない。
理由は、受信に影響する要素がSWR以外にも多数あるためである。
搬送波
変調の土台となる存在で、音声やデジタル信号をその周波数に乗せることで遠くまで伝えることが可能になる。
AMやFMなど、どの変調方式でも必ず必要な要素であり、受信機はこの搬送波を検出して元の情報を復元(復調)する。
抑圧波
SSBでカットされる搬送波。SSB方式では搬送波を抑圧して送信することで、効率的に遠距離通信を可能にしている。
インピーダンス
インピーダンスは電気回路における交流信号の流れやすさを表す指標で、抵抗成分とリアクタンス成分の合成値で示される。
アンテナと受信機を同軸ケーブルで接続する際、このインピーダンスが整合していないと、信号の一部が反射してしまい、受信感度の低下や送信効率の悪化につながる。
無線機やケーブルは50Ω、テレビ系の受信機器では75Ωといったように規格が統一されており、適切な整合が行われることで最大限の性能を引き出せる。
逆に、整合が不十分な場合は実効的な受信レベルが下がるだけでなく、送信時には機器の故障原因ともなりうるため注意が必要である。
リアクタンス
交流電流に対する抵抗成分の一つで、コンデンサやコイルが電流や電圧の変化に応じて示す「見かけの抵抗」である。
直流では0Ωあるいは∞Ωのように単純に動作する部品も、交流(とくに高周波)では周波数によって電流の流れやすさが変化する。
この周波数依存の抵抗成分こそがリアクタンスである。単位はオーム(Ω)で、抵抗(Resistance)と同じだが、性質は異なる。
種類と特徴
-
容量リアクタンス(Xc)
-
コンデンサが示すリアクタンス。
-
周波数が高くなるほど小さくなり(電流が流れやすくなる)、低周波や直流ではほぼ遮断する。
-
数式:Xc = 1 / (2πfC)
-
-
誘導リアクタンス(Xl)
-
コイル(インダクタ)が示すリアクタンス。
-
周波数が高くなるほど大きくなり(電流が流れにくくなる)。
-
数式:Xl = 2πfL
-
無線運用におけるリアクタンスの意味
-
アンテナの共振
アンテナは特定の周波数で「リアクタンスが0」になるように設計されている。つまり、コイル的な性質(誘導リアクタンス)とコンデンサ的な性質(容量リアクタンス)が釣り合って打ち消し合い、純粋な抵抗だけが残る状態を「共振点」と呼ぶ。このときアンテナの効率は最も高くなる。 -
マッチングの重要性
アンテナと受信機・送信機のインピーダンスが合わないとき、その差の原因の一部はリアクタンスである。たとえばアンテナが短すぎたり長すぎたりすると、容量性または誘導性のリアクタンスが残ってしまい、電力が効率的に伝わらなくなる。そのためアマチュア無線の現場では「アンテナチューナー」を使ってリアクタンスを打ち消し、インピーダンスを整合させる。 -
実際の受信体験
都市部のベランダにワイヤーアンテナを張った場合、長さが合わずに容量リアクタンスが強く残ることがある。このとき、受信機で短波放送を聞こうとしても感度が極端に悪い。チューナーをかませると途端に音が浮かび上がることがあり、「リアクタンスを補正した効果」を体感できる。
つまり、リアクタンスとは「周波数によって変わる見かけの抵抗」である。
アンテナや回路設計においては、このリアクタンスをいかに制御し、打ち消し合い、最適な共振点を作るかが性能を左右する。
理論的には単純な式で表されるが、実際の運用ではアンテナの設置環境や周囲の構造物によって予想外のリアクタンスが加わり、結果的に「なぜか聞こえない」「突然感度が良くなった」といった現象につながる。
オーム(Ω)
ドイツの物理学者ゲオルク・ジーモン・オーム(Georg Simon Ohm)が導き出した「オームの法則」にちなんで名付けられた電気抵抗の単位。
簡単にいうと、「電気の流れの機嫌を測るものさし」。しかし、単なる電気の単位ではなく、電気の通り道にかかる「抵抗感」そのものを数値化したものである。
1ボルトの電圧をかけたときに1アンペアの電流が流れる回路の抵抗値を1オームという。
数字だけ聞くと素っ気ないが、無線のアンテナ、オーディオの音作り、基板の設計など、あらゆる場面で顔を出す。数字は同じでも、その意味合いはシーンによって違って見える。
例えば、ヘッドホンを選ぶときに「インピーダンス32Ω」とか「600Ω」と書いてある。低インピーダンスは軽快に鳴るがノイズも拾いやすい、高インピーダンスは鳴らすのに力がいるが音が締まる。
人によって好みが分かれるのは、単なる数値以上の“味”をこのオームが決めているからである。
無線機とアンテナをつなぐ場合は、インピーダンスを「50オーム」でそろえるのが基本。もしアンテナ側が75オームだったり、変にズレていたりすると、電波は効率よく飛ばずに途中で跳ね返る。
例えると、ホースの太さと蛇口の口径が合わずに水が飛び散るようなものだ。
同期検波
搬送波に同期して復調すること。通常のAM受信機では「包絡線検波」と呼ばれる簡易的な方法が用いられるが、これは搬送波が弱いと雑音に弱く、フェージング(電波の強弱変動)があると音質が悪化する。
同期検波では、受信信号から搬送波成分を取り出し、それに同期した基準波を作り直して復調を行うため、フェージングやひずみに強く、弱い電波でも安定して明瞭な音声が得られる利点がある。
そのため高級BCL受信機や短波放送の安定受信に利用されることが多い。
AF(Audio Frequency)フィルター
受信機・無線機のオーディオ段で特定の音域を強調・抑制し、音声周波数帯域の信号を処理するフィルターを指す。
音声帯域の中で不要な周波数成分を除去することで、聞きやすくするためのもの。
たとえばハイカット(高音域を落とす)やローカット(低音域を落とす)が代表例。無線機の内部では高周波(RF)や中間周波(IF)の段階で不要な信号を落とすフィルターが使われるが、AFフィルターはその後の「音声帯域」に作用する。
マーカー発振器
周波数目盛りを較正するための発振器。無線受信機や通信機器の周波数目盛りやチューニング精度を確認するための信号源を発する調整機器である。
一定の既知周波数でパルス信号や連続波を送出し、受信機に入力することで、周波数表示の誤差や安定性を簡単にチェックできる。
航空無線や固定通信の受信機整備、実験、測定用途に用いられ、周波数管理や受信精度の確認に欠かせない。
AGC
Automatic Gain Controlの略。受信入力レベルを自動で制御する機能。
✅無線機器の調整・試験
試験電波
航空局や鉄道無線などが、機器点検などのために出す定常信号。時報的な性格もある。
レディオチェック
通話確認のために相手局に声をかける際の慣用表現。「Radio check, how copy?」