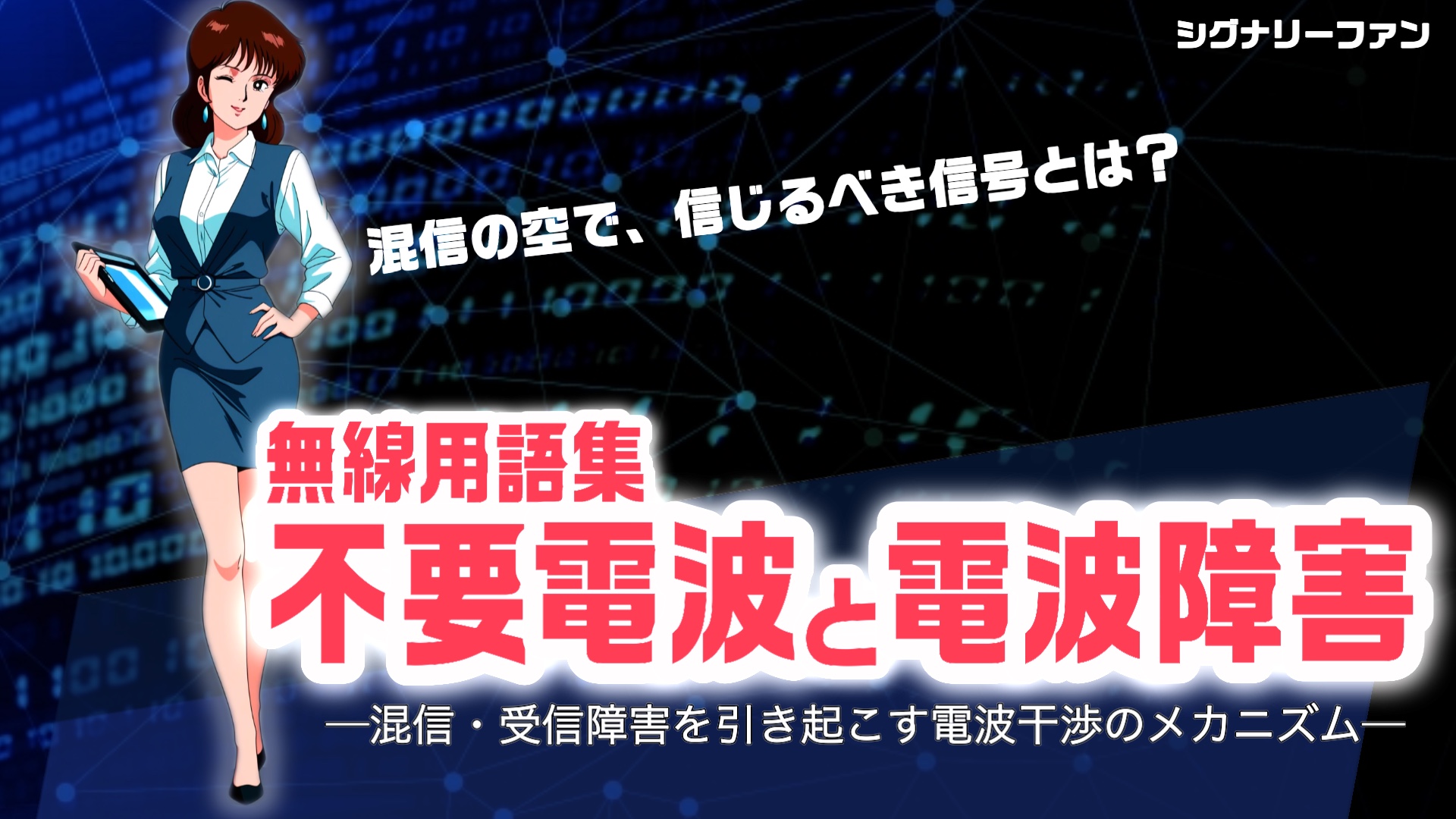気になる用語から各種記事にリンクで飛べますので、知識を広げながら無線ライフをより楽しんでください。
不要電波と電波障害など
スプリアス
送信機の特性や内部回路の非線形性などが原因となって発生し、本来の周波数以外に意図せず放射される不要な電波のこと。
通信に不要であるばかりか、他の無線局や機器に混信や妨害を与える可能性があるため、総務省によって規制対象である。
送信機の設計や運用においては、このスプリアスをできる限り抑制することが強く求められている。
カーチャージャー電波
ノイズの一種。車載充電器などから発生する不要電波。令和7年、航空無線にも重大な影響があると総通が指摘。
ゴースト
混信・誤同調による偽の受信信号、実在しない信号やノイズが特定周波数で聞こえる現象。
安価な受信機で起きやすい。
第二次高調波
送信した周波数の2倍の周波数で勝手に出てしまう不要な電波。
他の通信を妨害する原因になるので、本来なら無線機は「ローパスフィルター」で抑え込む設計になっているが、整流回路、インバーター、変圧器の磁気飽和などが原因で発生する。
例えば、145MHzで送信 → 290MHzにも弱い電波が出る。ごく稀に自衛隊のGCIを聴いてたら、近所のダンプの下品な交信が聞こえる。
💡 補足:実際の市販アマチュア無線機は「高調波抑圧 −60dB以下」みたいな規格を守って作られている。
イメージ受信
本来の周波数ではないのに“鏡”の位置で信号が聞こえる現象。
本物の信号と区別がつかず、「別の周波数の無線が聞こえる」など混乱を招く。
例としてアマバンドの144MHz帯をワッチしているときに、220MHz帯のGCIで強い信号があれば、それも受信してしまう。
やはり、航空自衛隊とダンプの運ちゃんが同じ周波数で“合同作戦”してるようなカオス受信である。
内部発信
受信機が自ら発生させる周期的電気信号。スプリアス源かつ、スキャン時に停止する要因。
DJ-X81ではUHF帯に41波もの内部発信があると専門誌で検証報告あり。
またIC-R30でもUHFには同程度の内部発信がある。スキップで飛ばすべし。
混変調
複数の電波が一つの受信回路やアンテナ内で混ざり合い、元の電波にない周波数が新しく発生してしまう現象。
イメージ受信、内部発信、混変調の三つは受信で厄介な現象である。
ノイズ
電波受信における雑音。無線受信において信号以外の不要な電波や電気的干渉であり、一般的に、人工的なもの(機器や電線由来)と自然現象(雷や宇宙由来)がある。
電源や照明、家電などから発生する高周波成分が受信機に入り込むことで、ザーッという背景音や弱い信号の埋没を引き起こすため、厄介である。
室内の蛍光灯、エアコン、ACアダプターなどのノイズ発生源を切ると、スケルチを解除したときの背景ノイズレベルが下がることは実際に観測される。
これは受信機に流入する不要信号が減るためであり、受信環境を整える基本である。
ノイズ源を特定して物理的に遮断するだけで、微弱信号の明瞭度も向上する場合がある。
カブリ込み
強力な隣接信号による受信障害。受信機に別の強力な隣接信号が入り込むことで、本来聞きたい電波の音声が潰れてしまう現象。
特に高感度の受信機で弱い信号を受信する際に顕著に現れ、受信音が雑音混じりになったり、まともに聞き取れなくなる原因にも。
電波の混信や受信機の選択度の不足が主な要因であり、アンテナの向きやフィルターの調整によってある程度改善できるが、信号自体の強さや周波数の近さによっては完全には防ぐことは難しい現象である。
周波数ドリフト
周波数のズレ。受信機の内部発振器の振動子の劣化などによる誤差により、周波数がじわじわずれる現象。HFで起こりやすい。
制限抵抗の値を大きくしたり、負荷容量を調整したりして駆動レベルを低くして対策する。
バンドパスフィルター
特定周波数帯とそれ以外を選別する仕組み。受信機や送信機に用いられる電子回路の一種で、特定の周波数帯だけを通過させ、それ以外の周波数を遮断する機能を持つものである。
無線受信においては、目的の信号だけを取り出して雑音や隣接信号の影響を抑えるために用いられる。
例えるなら、特定の音だけを通す耳栓のようなもので、不要な音や雑音は遮断し、聞きたい音だけをクリアに聴ける。
この特性により、弱い信号の受信や混信の多い環境での交信において、バンドパスフィルターの役割は非常に重要である。
フィルターの幅や形状を調整することで、受信機の選択度や信号の明瞭度を最適化できる。
アッテネータ / Attenuator
信号を意図的に弱くする装置。強すぎる電波が受信機に入ると飽和して混変調が起きる → 少し弱めて安定させる。
例えると「眩しすぎるライトをサングラスでちょうど良くする」感じ。 受信機には「ATT」スイッチが付いてることも多い。
感度
受信機が弱い電波を受ける性能。一般的には感度の高い受信機が優秀だが、高感度であればあるほど優秀というわけでもない。
確かに微弱な信号を拾いやすくなる利点はあるが、その一方で周囲の強い電波を一緒に取り込み、混変調や不要なノイズに悩まされることもある。
結果として、かえって目的の音が聞きづらくなる。また、どのように聞こえるかは使用する環境や受信対象によって大きく左右される。
同じ機種でも都市部と山間部では印象がまったく違うことがある。
したがって、カタログに載っている数値的な感度性能だけで判断するのではなく、実際に自分の耳でどのように聞こえるか、いわゆる「耳でのレベル(耳S)」を基準に見極めるのが一番確実。
購入の際は混変調の少なさなども総合的に判断したい。
信号対雑音比(S/N比)
信号の強さと雑音の比率を示す指標。目的の電波(信号)が、どれだけ雑音(ノイズ)に対して強いかを表す数値で、通常デシベル(dB)で表現される。
数値が高いほど、雑音に埋もれず明瞭に受信できることを意味する。
受信機の性能評価や回線品質の指標として重要で、放送や無線通信ではS/N比が一定以上でないと実用にならない。無線マニアにとっては「どれだけクリアに聞こえるか」を定量化する基準である。