街中で警察官の耳元にPチャンイヤホンが見えることはありませんか?

じつはこれ、署外で活動する警察官や機動捜査隊員が日常的に使用している重要な通信機器の一部なのです。
とくに制服警察官の場合、腰にトランシーバー型の無線機を装着しているのが一般的ですが、その無線とは別に、右胸のポケットには“タバコサイズ”の小さな黒い機器が入っていることがあります。
制服警察官の胸ポケットにある“謎の黒い機器”の正体とは?
この機器の名称は――「受令機(じゅれいき)」。

出典 NHK https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120083_00000
NHKの特集番組でも紹介されたこの受令機は、警察専用の無線受信機で、110番通報による現場出動指令を受け取るための専用機です。
番組では、地域警察官が実際に胸ポケットから黒い端末を取り出し、カメラの前に見せる場面が放送されました。
現在使用されているモデルの一つが「APR-WR1」。リチウム充電池を内蔵し、およそ5〜8時間の稼働が可能です。
使いやすさにおいては意見が分かれるところもあり、「扱いづらい」との声も一部で聞かれています。
「車載通信系」と「署活系」――2つの通信系統
警察無線には大きく分けて2つの通信系統があります。
-
基幹系(車載通信系)無線
VHF帯を使用し、広域にわたる通信が可能。主にパトカーやヘリコプターなど、移動体に搭載された無線機を通じて指令を受ける系統です。 -
署活系無線
UHF帯で通信する小エリア向けのハンディ無線機システム。各署の管轄区域内で活動する警察官が、所属署とのみ通信を行う警察署単位の系統です。
つまり、パトカーなど“移動体”に乗務する隊員には広域カバーの基幹系、一方、交番勤務員や地域警らの警官など“徒歩・自転車で活動する警察官”は、狭い範囲で確実に連絡が取れる署活系を主に使っています。

このうち、受令機は警察本部が警ら用無線自動車および警察ヘリ、警察船艇向けなどの移動体に指令を出す『基幹系(車載通信系)無線』を聴取できます。

ただし、こちらは捜査専務系という専用チャンネルを使って交信。
しかし、無線機と違って送信する機能はありません。
言うなれば、警察本部通信指令室から一方的に指令を受ける『警察無線専用ポケットラジオ』。
パトカーに乗らない警察官が使う「受令機」と通信システムのしくみ
パトカーに乗っていない警察官――たとえば、交番勤務や、車載無線のないミニパトで地域を巡回する署員、そして自転車で移動する署員は、どのようにして基幹系警察無線を聴取しているのでしょうか?
その答えが、「受令機」です。
受令機は、胸ポケットなどに収納して持ち歩けるコンパクトな端末で、車載無線のない警察官でも本部や指令センターからの無線をリアルタイムで受信できます。
もちろん、私服で行動する機動捜査隊員なども同様に、現場で受令機を携行し、状況把握に活用しています。
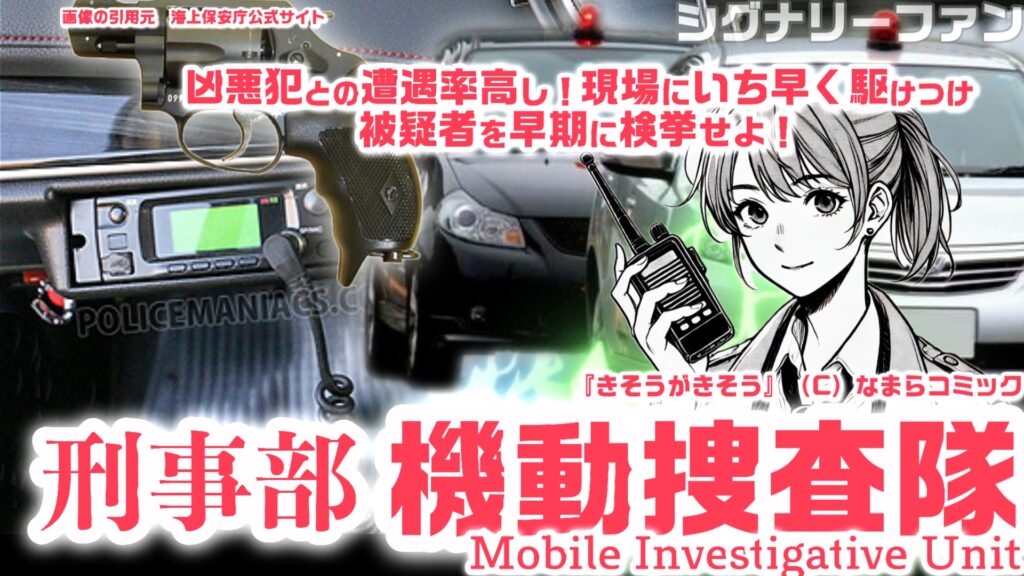
受令機の歴史
かつて車載通信系がアナログ方式だった時代には、「UR-1」「UR-2」「UR-3」の3種類の受令機が配備されていました。
いずれもタバコの箱と同程度のポケットサイズで、県内系および共通系の2つの周波数帯に対応。水晶振動子を内蔵し、スイッチ操作により任意の周波数を切り替えることが可能でした。
アンテナは本体に内蔵されており、富士通製のUR-1の取扱説明書には、イヤホンコードがアンテナの役割を兼ねていることが明記されており、使用時はコードを束ねずに伸ばすよう推奨されています。
これらの受令機はすべて、トーン信号による選択呼出機能(セルコール)を搭載しており、個別呼出し・グループ呼出し・一斉呼出しといった各種の呼出方式に対応。
ポケットベルの使用形態にも似た運用がなされていました。
たとえば110番通報が入ると、通信指令室では即座に該当する所轄署の外勤警察官らに対し、受令機のグループ呼出機能を用いて「ピーピー」「ピュー」といったトーン信号を約3秒間鳴らして注意喚起。その後、指令内容が音声で送信されるという流れです。
UR-2については本体にスピーカーを内蔵しており、イヤホンに加えてスピーカーでも受信音を聴取できます。
またUR-3には専用のアダプター型スピーカーが用意されており、交番などでは据え置き型スピーカー受令機のように使用することも可能でした。
さらに、UR-3は音量を最小にしても完全な消音にはならないという特有の仕様です。
その後、基幹系のデジタル化にともない、新たにデジタル対応の受令機「UR-100」が配備。サイズはアナログ時代のUR-3とほぼ同等で、単三電池1本でおおよそ24時間の連続使用が可能です。
現在も運用の基本は大きく変わっていませんが、デジタル方式への移行により、従来のセルコールは廃止され、代わってデジタル信号音による呼び出し方式が採用されています。
他県の警察本部の通信圏内に入れば、全国の警察で共通配備の受令機で傍受可能
警察無線は基本的に都道府県警ごとに独立して運用されていますが、現行の受令機は全国で共通仕様となっており、すべての都道府県警で同一のタイプが配備されています。
このため、たとえ他県の警察本部の通信エリア内に入っても、所属県警から貸与されている受令機で、その地域の無線通信を問題なく傍受できます。
たとえば、山梨県警の警察官が東京都内に移動した場合でも、自身に貸与された山梨県警の受令機を使って、警視庁の無線を受信可能です。
これは大規模災害などで広域的な警察活動が必要になった際、応援先の警察本部の指令内容を正確に把握する必要があるためで、こうした運用を前提に受令機の仕様が統一されています。
この事実については、下記に示す報道資料により裏付けられています。
捜査関係者によると、元警察官は山梨県警捜査一課の警部補だった〇九年八月、警察が使う受信機(受令機)二台を東京都八王子市内に持ち出し、警視庁の無線を傍受。
~略~
警察無線は過去には革マル派の活動家が警察無線を傍受したとして逮捕された事件もあり、外部から傍受、解析されないよう対策を強化してきた。
しかし警察備品の受信機を使えば他の都道府県警の無線でも傍受でき、「警察官なら悪意があれば(傍受、録音して)持ち出せてしまう」(捜査幹部)。
警察庁情報通信局の担当者は「広域災害などの際、他地域の無線を聞けるようにする必要がある。
各都道府県警を通じ、無線機の管理体制を厳格にしていくなど対応したい」と話した。
出典 https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201908/CK2019082302000278.html
また産経新聞でも同様に報じています。
警察無線は暗号化され、外部の機器による傍受は不可能とされる。都道府県警ごとに別の系統で運用されているが、他警察の通信圏内に入れば警察共通のイヤホン型無線受令機で受信できるという。
出典 https://www.sankei.com/affairs/news/190823/afr1908230009-n1.html
警察装備品は原則として厳重管理されており、多くの都道府県警では、非番や休日であっても装備品の私的持ち出しはNGです。
例外的に、警察手帳の携帯を非番中にも認める運用を採る警視庁などもありますが、基本的には「商売道具」を自宅に持ち帰ることは許されていません。
ところが、受令機に関しては例外的な扱いを受ける場合があります。これは、非番中でも緊急招集に即応できる体制を整えるためで、持ち帰りが黙認・許容されている事例も存在しています。
しかし、この運用が裏目に出ることもあります。実際、山梨県警の不祥事では、こうした装備品の持ち出しが一因となった可能性も否定できません。

受令機のまとめ
このように、活動中の警察官が耳にイヤホンをしていたら、それは腰の署活系無線とは別に、胸ポケットに入れた受令機にてパトカー向けの無線「車載通信系」で流される警察本部通信指令室からの緊急配備情報や注意喚起などの指令を聴取しているというわけです。
そして本署と連絡をとる場合は腰の署活系無線機(PSW)を使用しています。

なお、パトカー乗務中の警察官であっても、現場に到着後に一時的に車両を離れて捜索や対応にあたる場合は、車載の基幹系無線からの指令を受け取れなくなります。
こうした状況に備え、警察官はあらかじめ受令機をポケットに携行し、イヤホンを通じて基幹系の指令を常時受信できるようにしています。
しかし、これまで使用されていた署活系のハンディ無線機や受令機には、電波が地下や建物内に届きにくいという課題があり、重要な指示の伝達が滞るケースも見られました。
この問題に対応するため、平成23年以降、全国の警察本部では順次、新たな通信インフラが導入されました。
それが、旧・署活系無線の後継として位置づけられる『新・署活系無線PSW(Police Station Walkie talkie)システム』と、データ通信機能を活用した『PSD(Police Station Data terminal)システム』を中核とする『地域警察デジタル無線システム』です。
この新システムの導入により、警察官は屋内や地下でも安定した通信が可能となり、迅速かつ確実な指令の伝達が図られるようになりました。

他の関連記事もぜひご覧ください。



















































































































