無線とはやや離れますが、この趣味界隈では「お巡りさん」とは切ってもきれない関係にあります。
ここでいう「お巡りさん関係」とは、警察活動そのものを意味するのではなく、無線趣味と隣り合わせにあるパトカー、警察無線、専門誌などに関連する事柄をまとめたもので、いわゆるマニア界隈の用語です。
無線用語の”番外編”として、無線用語集の一部に位置づけ、広義の意味で掲載しています。
この趣味界隈で語られる「お巡りさん」との関わりについて整理しました。
なお、パトカーや警察装備全般についてはシグナリーファン@セキュリティでも特集しています。
関連リンク
以下のリンクも併せてご参照ください。
✅お巡りさん関係
警察無線
警察無線は現在、警察専用のデジタル方式に完全移行しており、市販の受信機では受信不可能。

しかし、80年代の「おもしろ無線受信」「アクションバンド受信」の定番といえば、この警察無線、通称“Pチャン”であった。
当時は、多くの受信愛好家が最初に耳を傾ける存在が警察無線であり、事件・事故の最前線の生々しいやり取りをリアルタイムで聞けた。
警察無線を傍受し、犯人を発見した市民からの情報提供により検挙された実例が当時報道されているが、警察当局は“困惑”したという。

その後、MPR、APR、そしてIPRへと順次更新され、通信の秘匿性と効率は飛躍的に高まった。
現在では完全デジタル化によって外部からの受信は法的、技術的にも不可能である。
宰領通信
「宰領(さいりょう)」とは警察通信において“通信の統制”を意味し、係る無線通信を管理・制御する役割を表す重要な概念である。
通信指揮の秩序を保つため、警察本部の通信指令課長が「通信統制官」として、通信の優先順位を決めたり、無線局の運用全般を統括し、警察活動を円滑に進める重要な役割を担う。
警察における無線通信はパトロール、110番通報、緊急配備など、緊迫かつ迅速な対応が求められる。
その中で、通信の優先順位を決めたり、割り込み通信を整理したりするのは極めて重要であり、「宰領通信」はその根幹を成すわけだ。
警察の指令卓などといったプロの現場でも、最終的にマイクを握って判断を下すのはオペレーターであり、「オペレーターの腕前」という言葉が存在するように、交信がスムーズに進むかどうかは人間の技能に大きく依存する。
事実、アナログ警察無線の頃、宰領通信である警視庁通信指令センターには、捌き方の上手い名物職員が存在し、受信家には個別のファンが多数いたようだ。

相手の電波をどう聞き取り、どう応答するか、あるいは混信やフェージングの中から必要な信号を選び取るかといった能力は、単なる機械任せではなくオペレーター自身の経験に裏打ちされた技術といえる。
したがって、無線の世界において「オペレーター」とは、機械の延長線上にある存在ではなく、通信そのものを成立させる最後の要となる人的リソースの呼称である。
参照:https://www.npa.go.jp/laws/notification/kunrei/1965kunrei3-jouki.pdf
TLアンテナ
(この趣味界隈では)警察無線用アンテナの一種。90年代に普及した自動車電話用アンテナを模した覆面パトカー用アンテナを指す。

TAアンテナ
(この趣味界隈では)警察無線用アンテナの一種。カーナビ&カーテレビ用ダイバシティアンテナを模した覆面パトカー用アンテナのこと。

ユーロアンテナ
(この趣味界隈では)警察無線用アンテナの一種。『MG-UV-TP』のこと。150MHzと350MHzの2波共用。
つまり…市販されていないが、技術的には351MHzのデジ簡でも使える。しかし、電波法では「違法」。

💡 補足:なお、外見そっくりのタクシー無線用アンテナ『MG-450-TP』が市販されており、こちらはアマチュア無線の430MHzでマッチング良好。

ハンガーアンテナ
(この趣味界隈では)警察無線用アンテナの一種。覆面パトカーの車内にさりげなく置かれている衣類用ハンガー…に擬態した無線アンテナ。
移動警電
警察部内用の内線電話(FMでMCA方式)。外線発信も可能。後述のWIDEに廃止統合。
WIDE
警察無線の一種。移動警電の後継。Wireless Integrated Digital Equipment―統合デジタル無線機器。最新のIPR無線に統合。

Pチャンイヤホン
Pチャンイヤホンはテレビ局、ラジオ関係の放送局で使用されている業界向けのイヤホンである。そして警察業界でも何十年にもわたって使用されている。高性能イヤホンである。
無線交信の受信音を快適に聞くための小型イヤホンであり、警察では主に受令機で利用されている。

受令機
受令機は警察無線を受信するための警察官専用受信機。全国で同一仕様になっており、他の警察本部の管轄へ出向いても、その警察本部の無線の周波数に同調してくれる優れもの。
ラジオライフ
『ラジオライフ』(略称・RL)は、受信趣味の裾野を広げる専門誌として1980年6月に創刊された無線関連専門誌である。
創刊以来、この趣味界隈の読者に親しまれる存在であり、キャラクターにはコウモリが採用されている。2025年より、従来の月刊発行から隔月発行体制へと移行した。
同誌は、アマチュア無線や業務無線など多様な受信趣味を扱うだけでなく、警察ウオッチング文化の普及にも寄与した雑誌として知られている。
その中核的存在として知られるのが大井松田吾郎氏である。
氏はパトカー写真と警察無線研究の第一人者であり、RL誌上では警察無線の技術解説や受信機レビューなど、幅広い分野で活躍している専門家兼プロライターである。ファンからは「師匠」の愛称で呼ばれている。
特に人気を博した「交通取締車両図鑑」系の記事や、『パトカーマニアックス』では、覆面パトカーを中心とした高精度な写真と、警察無線機の最新動向をわかりやすくかつ多層的に分析する手法が読者に高く評価された。
警察無線がまだアナログ方式で運用されていた時代には、受信報告や投稿記事を通じて読者同士の交流が盛んであり、雑誌を中心に独自の受信文化が形成された。
専門的かつ閉じた趣味領域を扱うがゆえに、週刊誌など一般メディアから誤解の上で批判の的ともなったが、ラジオライフ誌は一貫して「受信は自由」を旗印に、マニア的探求心と技術的興味を社会に提示し続けている。

RLは、警察無線のみならず航空無線の分野にも早くから注力してきた媒体である。
特に航空自衛隊のGCI(地上要撃管制)に関しては、長年にわたり非公開領域に極めて近い情報を丹念に追跡し続けており、その蓄積は他誌の追随を許さない。
掲載される「管制周波数リスト」や「交信の解析」は、現在に至っても研究資料として高く評価されている。
なお、『ラジオライフ』の過去号や特集の一部は2025年10月現在、アマゾンの「Kindle Unlimited」サービスでも配信されており、月額980円のみで追加料金なしに楽しむことができる。
往年の受信レポートや覆面パトカー特集、BCL、GCI記事まで、当時の熱気そのままにスマートフォンやタブレットで手軽に再読できるのは、若い世代にとっても新たな知識の発見につながる一助になるかもしれない。
「Kindle Unlimited」では、三才ムックのアマチュア無線・受信関連書籍を含む100万冊以上の電子書籍(小説、コミック、雑誌、写真集など)が読み放題の対象となっており、当時読者が『ラジオライフ』のバックナンバーを再読するのにも最適。
また、1980年代後半から1990年代にかけてのRLでは、漫画家・横山公一氏の存在も欠かせない。親しみやすい絵柄とユーモラスな四コマ漫画で、航空祭からGCI、さらには覆面パトカーまで幅広いテーマを扱い、誌面に魅力を添えた。
横山氏は現在も『むせん部部活中!』などの同人活動を続けるほか、関鉄観光バスのマスコットキャラクターデザインを手がけるなど、精力的に活動を続けている。
さらに、『ラジオライフ』誌におけるパトカーネタには、当時の「婦警さん(死語な)ブーム」も密接に関わっている。
1980年代に盛り上がりを見せた“婦警さん投稿写真コーナー”の背景を、バックナンバーを通じてたどると、当時のこの趣味界隈が実に多角的であった事実が浮かび上がる。
一方、RLには婦警さん写真に密接した絵師がもう一人存在する。イラストレーターの森伸之氏である。
森氏は日本のサブカルチャー史の中でも極めて重要な人物であり、「制服女子高生を描く作家」として一般に知られる。
森伸之氏はまた、白倉由美氏の作品において制服デザインを担当した経歴もあり、当時の「(とくに女性の着用する)制服」というモチーフの多面的な展開を象徴する存在でもあった。
だが、意外にも職業女性(ショム課OLから2等陸士まで)も描いており、同誌でも警察官・自衛官・消防吏員・海上保安官など、公職に従事する女性らの制服姿をイラストで数多く発表していた。社会的な規律や権威を象徴する女性像を描くことで、女性のキャリアや主体性という視点を提示し、当時の読者に新たな印象を与えた。
これらの作品群も、1980〜90年代にかけての「制服文化」ブームの一端を示すものであり、サブカルチャー史の中でも貴重な資料的価値を持つ。
なお、当サイトでは『ラジオライフ』誌の内容を一次的資料として参照・活用しており、この場を借りて謝意を申し上げたい。
公ギャル
女性公務員(制服系)の俗称。上述のRLの人気企画の一つだった「女性警察官投稿写真コーナー」。特に公開行事での華やかなカラーガード隊員の写真が多く投稿された。
彼女たちをRLでは「公ギャル」と呼称。「公ギャル フォトブック」まで出版している。90年代には自衛隊にも女性が増え、WAC・WAVE・WAF(女性陸海空自衛官)の写真も増加した。例えるならこのような感じである。↓
アクションバンド電波
専門誌名。RLの元編集長が87年に創刊したかつてのRLのライバル誌。略称は『AB』、キャラクターは海老。2005年廃刊。
誌面は過激そのもので、送信改造のハウツーまで堂々と解説する攻めの編集方針。

当時、無線受信マニアは「アクションバンダー」と呼ばれたが、RL誌はAB誌の登場後は呼称を「おもしろ無線」に変えたとか。
1992年公開の映画『七人のおたく』では、「受信おたく」役の少女監修も担当し、リアルなマニア表現に一役買った。
💡 補足:2021年には出版元の株式会社マガジンランドが閉業し、ABの歴史は幕を下ろした。
パックスラジオ
八王子の無線機関連業者。『アクションバンド電波』誌の創刊に関わった無線ショップ。
💡 補足:なぜか警察グッズも大量に販売しているマニアに知られた店。
公益無線受信者手帳
上述のパックスラジオが製造販売していた某マニア向けグッズ。旧・警察手帳を模した本格手帳。“警察規則に基づく同一装丁”となっている。
表紙に「公益無線受信者手帳」と書いてあり、威厳ありげな特殊コーティングありの牛皮仕様(警視庁タイプの警察手帳に近い外装仕上げ)。
現在もオークションで高額で取引されており、一定の需要があるものとみられる。
















































































































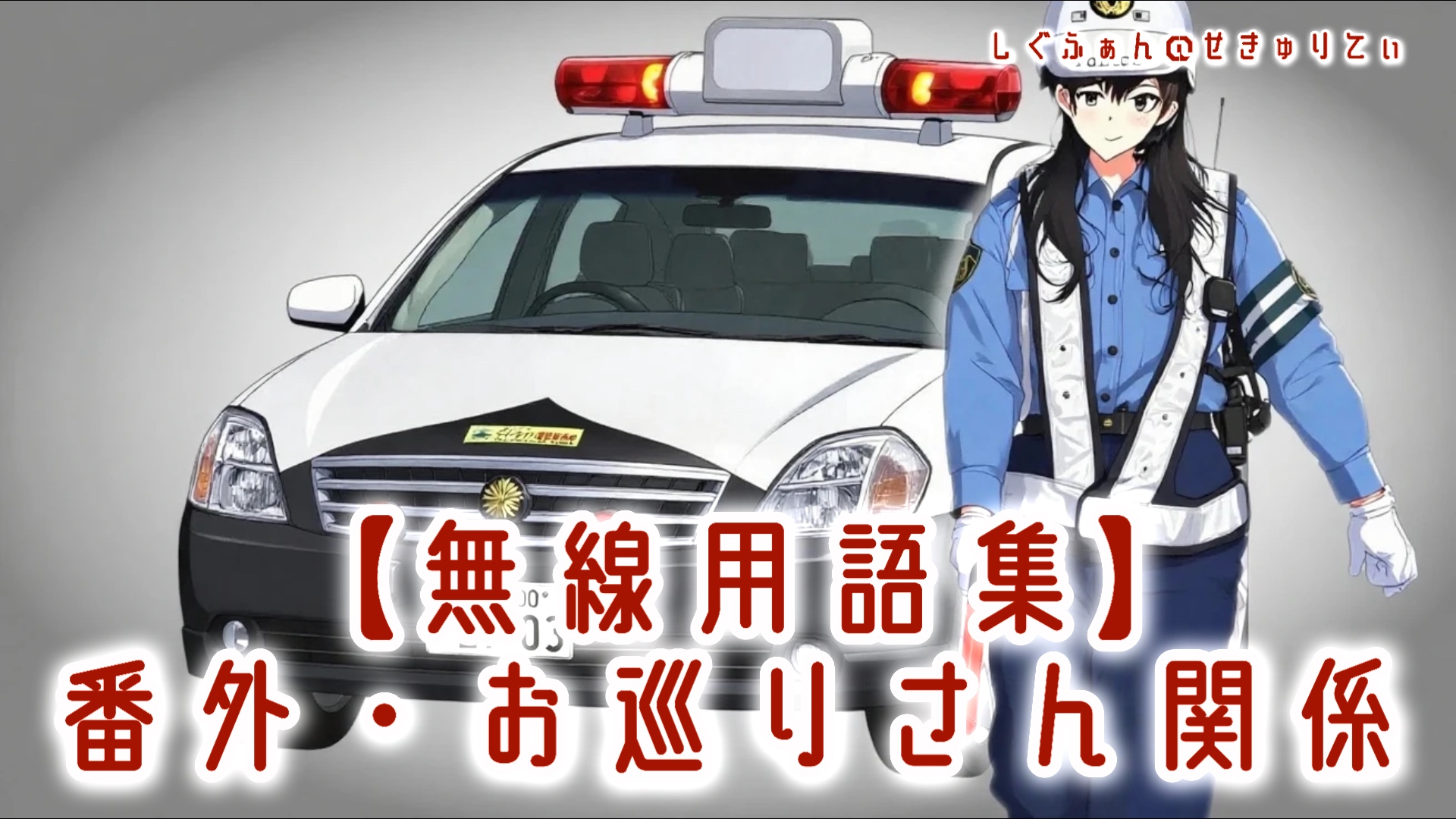
![ラジオライフ2025年 12月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51tVFBsRO6L._SL160_.jpg)


