2025年9月30日をもって、これまで紙で発給されていた無線局免許状は廃止され、同年10月1日から免許される無線局については、デジタルデータ化されました。このため、紙の免許状は新たに発行される事はありませんのでご了承お願いいたします。なお、無線局免許の制度自体は、今後も変わりません。
『無線局免許状』と『無線局免許証票』
これまで自宅でアマチュア無線機を使用する場合、困難でない限りは無線局免許状(局免)を無線機の常置場所の見やすい場所に掲げることが、電波法施行規則第38条第2項で定められていました。
免許状は、主たる送信装置のある場所の見やすい場所に掲げておかなくてはならない。ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない
それまでの電波法施行規則第38条第2項
しかし、平成30年3月からは、電波法施行規則等の一部改正により『掲げる義務』が廃止されました。総務省ではその理由を以下のように説明しています。
免許状は、これまで、主たる送信装置のある場所に掲示することを義務としていましたが、無線局に備え付けておくことでも支障がないことから、免許状を掲示する義務を、平成30年3月1日をもって廃止します。
なお、船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局の免許状については、従来どおり、掲示することを義務としています。また、アマチュア局の免許状についても従来どおり、無線設備の常置場所への備え付けとしています。
典拠元 総務省総合通信局 http://www.tele.soumu.go.jp/j/haishi_kanwa/
つまり、局免は掲げる義務がなくなった代わりに、備え付ける義務へ変更になったのです。
おっと、『従事者免許証』については無線の運用中は必ず携行してくださいね。

車に無線局免許状は積むの?
一方、「移動する局」として、ハンディ機を使って山の上で運用したり、車に積んでモービル運用を楽しむ場合、無線局免許状(局免)の扱いはどうなるのでしょうか?
「局免はカバンに入れて持ち歩くの?」「車の中に積んでおくの?」と思う方もいるかもしれません。
その答えは―『NO』です。
たとえ「移動する局」として免許を受けたアマチュア無線局で、モービル運用中でも、無線局免許状は“無線設備の常置場所”に備え付けなければならないと、法令で定められています。
車は常置場所として届け出ることはできないため、車に積んだままの状態で運用する目的であっても、通常は住所を常置場所として申請します。
これは、車に無線機を載せる場合、その運用は一時的な運用とみなされるためです。
したがって、局免は常置場所(自宅など)に保管する義務があるのです。
では、車に積んだ無線機を使って運用しているとき、取締り当局側から「この人、ちゃんと免許持ってるの?」と確認できないのでは? という疑問が出てきます。
とくに、モービルや移動運用中に職務質問されると気になりますよね。
無線局免許証票(平成30年3月1日に廃止されました)
そのため、無線局免許状を現場に備え付けられない「移動運用」などのケースにおいて、免許を受けていることを証明するために発給されていたのが『無線局免許証票』です。
この免許証票は、総務省令・電波法施行規則に基づいて発行されていたもので、「移動する無線局」のための補助的な証明書です。これには歴史もあります。
制度としては、1960年に「簡易無線局の証」として創設されましたが、1967年にいったん廃止。その後、1970年(昭和45年)に『無線局免許証票』として再度制度化され、当初は名刺サイズのカード型で、車両のダッシュボードなどに掲示することが求められていました。
1991年には形状が改められ、シールタイプへと変更されました。
なお、アイコム社の公式ウェブサイト内の連載コラムでも、このモービル運用時の免許制度(従免・局免)や証票について詳しく解説されていますので、興味がある方はぜひ一度ご覧ください。
移動する局が携帯しなければならないのは何か、友人に聞いてみました。
「無線局免許状と従事者免許状じゃないかな。」
「正しくないですね。」
「正解は従事者免許証と無線局免許証票の2点セットです。」
「免許状はいらないの?」
「免許状は常置場所に掲げておくのが決まりです。」
「免許状と従事者免許証があれば良いと思っていました。」
「それは誤りです。」典拠元 アイコム株式会社公式サイト https://www.icom.co.jp/beacon/talk/002041.html
そう、車に局免を積まない代わりに、この無線局免許証票(シール)を必ず備えることが決まっていましたが、無線局免許証票は2018年3月で廃止されました。
なお、筆者は何度もモービル運用中に職務質問を受け(新任警察官の実践実習の相手役に都合よくされている感じがしますが)、そのたびに従事者免許を提示しているのですが、新任警察官もその辺は怖い巡査部長から厳しく指導されているようで、抜け目なく「もう一つ、免許ありますよねェ?」と言って「もうひとつの免許」である局免も求めてきます。
筆者はもちろん、備え付けが義務である無線局免許証票のシールを見せるのですが、一部の警察官は「ダンプとかだと免許状積んでますけどねェ」と言うことがあります。
警察官の中には『局免は自宅での掲示、それに代えるものとして証票がある』ことを知らない場合があります。

筆者はそのたびに「移動する局の場合、無線局免許証票で証明できると法律で明記されています」と説明してきました。
いつかはアイコムさんのコラムみたいに「(局免を積むのは)正しくないですね」とか「(ダンプがそれをやっていたとしても)それは誤りです」とか言ってみたいですね。
「このシールが無線機が無線局免許状を正当に得ているということを証明します」
典拠元 「はじめてみよう アマチュア無線」 丹羽一夫 CQ出版社
ハム本の解説者で知られる丹羽一夫氏も上記の様におっしゃっています。
シールを貼り付ける場所は無線機本体の見やすいところであれば、とくに規定はありませんが、すぐに剥がれないようにハンディ機なら電池ケースの裏フタの内側に貼り、モービル機でも剥がれにくく、万が一の取り締まりの際にすぐに見せられる場所に貼っていました。
警察官に停止命令を受けて無線の免許を見せてくださいと言われたなら、まず従事者免許証を見せて 「局免もありますか?」と聞かれたら無線機に張り付けてある証票シールを見せていました。
『局免のコピー』を積むと効果的?
『局免のコピー』をクルマに積むことは、むしろハムの間でも積極的に勧められています。しかし、前述したアイコムさんの公式サイトにあるコラム内には『局免のコピー』に関しても触れられており、その中でその効力については『気休め程度の効果』と懐疑的な見方をされています。
「免許証票」は平成30年3月で廃止
現在は廃止されています。
これは平成30年2月1日に交付された「無線局免許手続規則の一部を改正する省令」にともなう措置で、平成30年3月1日までにアマチュア局の免許証票が廃止されました。
それ以降はアマチュア局の移動する局(いわゆるモービル運用の場合)の開局申請、再免許申請ならびに無線機の増設、または取替の変更申請時、証票(シール)の発行はされません。
今回の廃止の理由を総務省では以下のように説明しています。
免許証票については、無線局の免許状を備え付けることが難しい陸上移動局等が「免許を有していること」を明らかにするため、免許状の代わりに備え付けることを求めてきた経緯がありますが、総合無線局監理システムにおける無線局データベースの充実を踏まえ、免許状や事項書等の備え付け書類による無線局管理でも支障がないと判断したことから、アマチュア局においても免許証票を廃止するものです。
引用元 http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/E/Ama/saishin/amah300226.htm
なお、総務省によれば、すでに発給されている免許証票(シール)はそのまま無線機に貼付していても問題はないとのことです。
免許証票(シール)廃止によって警察の不法無線局取り締まりはどう変わる?
では、これまで行われてきた警察さんによる『もう一つ免許ありますよねぇ』に対して「ほい」と見せて、「あっ、ありますね…」で無罪放免されていたビックリマンシールより偉い証票シールがなくなった現状、確認はどうなるんでしょうか。
今回の証票廃止について、不法無線局の取り締まりに支障は出ないのか、一部で指摘されています。
これまで無線機に貼られていた免許証票のシールが廃止されることで、今後の不法無線局取り締まりはどう変わるのか、実際、多くのモービルハムや移動運用愛好家は注目されているのではないでしょうか。

当局者である総合通信局と警察合同による電波検問なら問題ないのでしょうが、とくに「警察単体での職務質問からの無線設備確認」が今後どう変わるのか、警察官の『もう一つ免許ありますよねぇ』という怪しいセリフがどう変わるのか、私たち正規のアマチュア局にとっては興味深いところですよね。
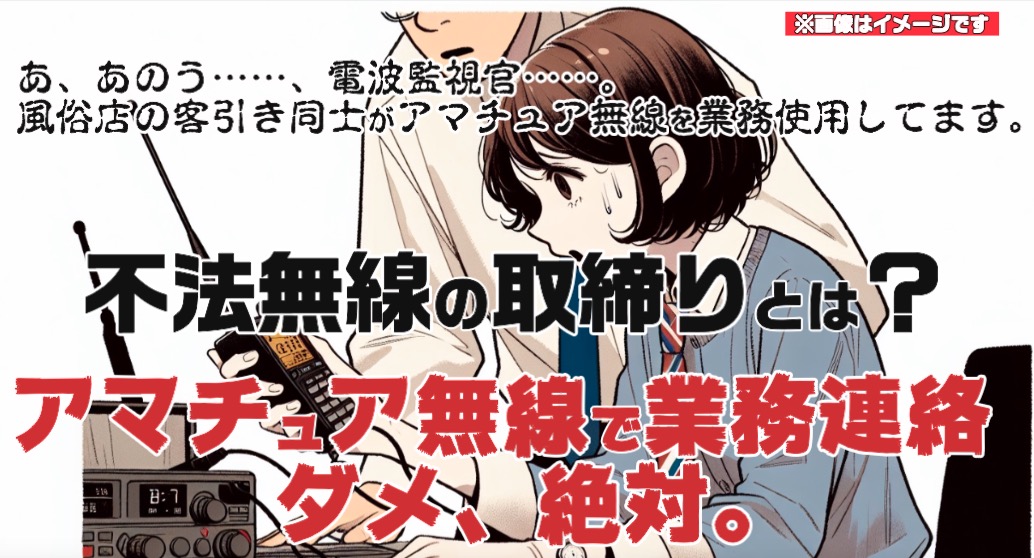
これについて総務省は証票廃止後の取締りにおいて、正規局がどのように当局に身の証を立てるのかという個人からの意見に対して以下のように説明しています。
提出された意見
「総務大臣又は総合通信局長が発給する証票の様式等を定める件等を廃止する件」
アマチュア無線では移動する局の送信装置に対して1台ずつ証票が発行されている。今までは、証票により正規局である、もしくは正規に登録されている無線機であると証明するものだったのだが、今後はどう身の証をたてるのか、違法局をどう見分けるのか。総務省の考え方
今回の制度改正の趣旨及び概要について、引き続き、警察庁や海上保安庁等の関係機関に説明してまいります。
引用元 総務省公式サイト http://www.soumu.go.jp/main_content/000521920.pdf
総務省の見解によれば、今回の制度改正の趣旨と概要については、すでに警察などの取締機関へ説明済みであるとのことです。
つまり、正規のアマチュア無線局と不法局を識別することに支障はないという立場です。
この総務省の公式なコメントを信じるならば、たとえば我々正規のアマチュア局が路上で警察による電波取締りに遭遇したとしても、無線機に免許証票のシールが貼られていないことだけを理由に、警察官から疑われることは本来ないと考えてよいでしょう。
また、総務省の説明によれば、今後は『総合無線局監理システム(PARTNER)』を通じて、警察官がその場で従事者免許証の番号を照会すれば、当該従事者が正規の無線局免許を受けているかどうかを即座に確認できる仕組みとなっています。
この「PARTNER」に対して警察官がどのようにアクセスして照会を行うのか、その具体的なプロセスは公表されていませんが、次のような方法が想定されます。
これは、普段の職務質問で運転免許証による身元照会を行う流れと同様と見られます。
なお、2018年から警察の移動体向け無線システムにはIPR(Internet Protocol Radio)という新型無線が導入されており、他省庁のデータベースとよりスムーズに連携可能なインフラが整ってきているようです。
いずれにせよ、こうした技術環境とシステムの整備により、移動する無線局に対して発給されていた「無線局免許証票(シール)」の制度は、現行では廃止となったわけです。
ただし、アマチュア無線運用時には、以下の2点が引き続き義務として求められます。
-
運用時は従事者免許証(従免)を携帯
-
無線機の常置場所における無線局免許状(局免)の備え付け
これらは法令上の義務ですので、改めてしっかりと確認しておきたいところです。























































































































