アマチュア無線は単なる通信手段ではなく、趣味として世界中の仲間と交信を楽しむ文化としても親しまれています。このページでは、そんな無線を題材にした作品や、無線を通じて個性を発揮するキャラクターたちをご紹介します。
アニメ、漫画の中で描かれる無線の魅力は、現実の趣味ともリンクしており、登場人物の人間関係やドラマをより豊かにしています。無線を知らない方でも、その世界観や楽しさを感じていただける内容です。作品ごとの設定やキャラクターの特徴にも触れながら、無線趣味の面白さをお伝えします。
✅アマチュア無線など趣味の無線を扱った作品
ロードキラー
アメリカで制作されたCB無線を題材とするサスペンス・サイコスリラー映画である。作中では、趣味でCB無線を楽しむ登場人物たちが、軽い悪ふざけのつもりで交信を行う。しかし、その遊び心が思わぬ恐怖や混乱を招き、事態が急転する様子が描かれている。
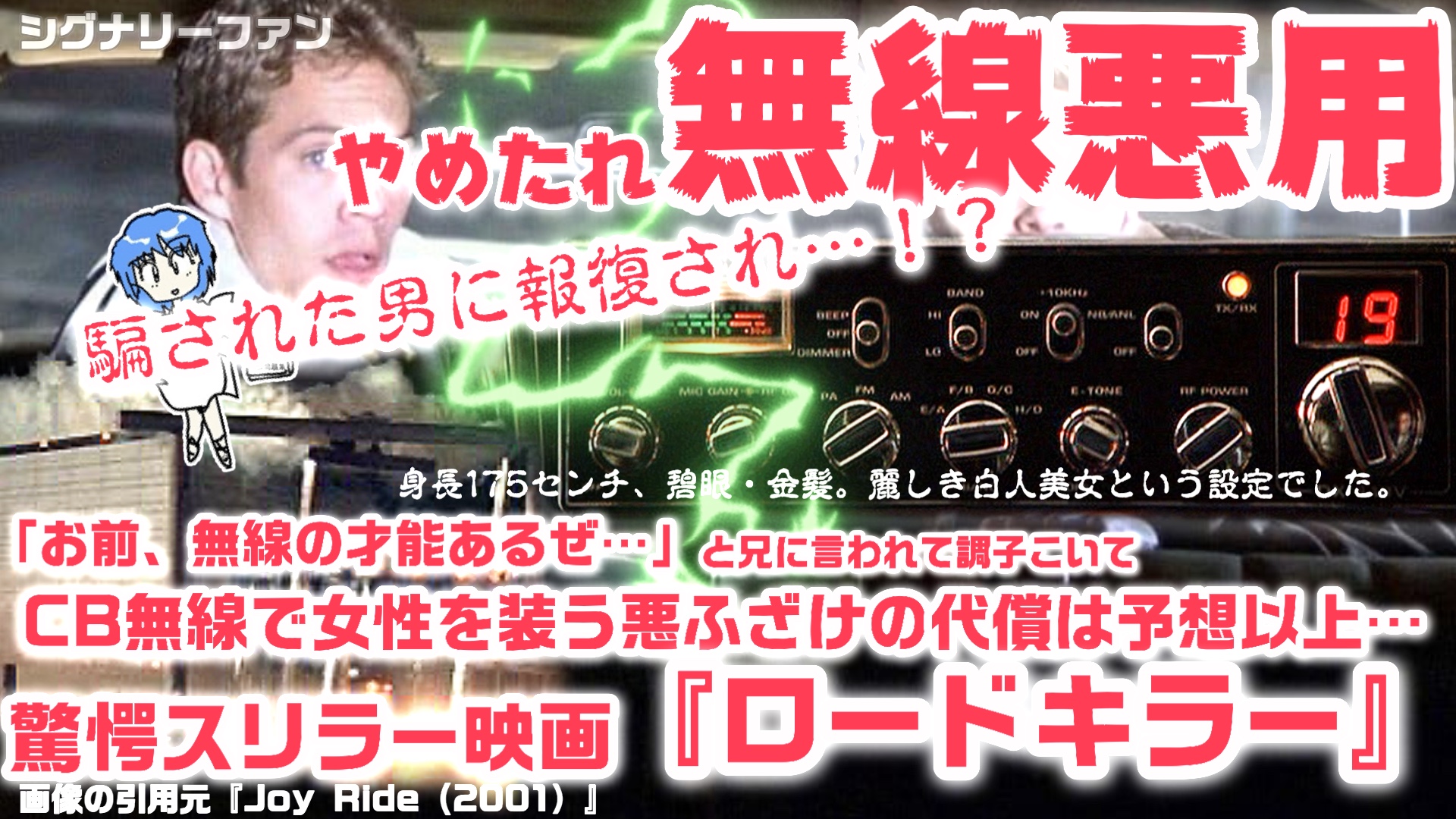
映画は娯楽作品ではあるが、無線を扱う者にとっては警鐘とも言える内容である。CB無線は一般市民が手軽に扱えるため、ちょっとしたいたずらが現実世界では法的・安全上のトラブルに直結する可能性がある。作中の展開はオーバーではあるが、「無線で遊ぶときには節度を持つべし」という教訓をユーモラスに無線家に提示している。
また、映画の冒頭ではCB無線特有の軽妙な交信文化や、仲間内でのジョーク、呼出し名(ハンドルネーム)のやり取りなども描かれ、コミュニケーションの楽しさを垣間見ることもできる。観る側は思わず「自分もついやりたくなる…けど、現実では絶対やめよう」と身につまされるだろう。
崖の上のポニョ
『崖の上のポニョ』(2008年公開、直近では2025年8月22日に地上波放映)は、単なるジブリアニメにとどまらず、アマチュア無線ファンにとっても興味深い描写を含む作品である。
劇中、嵐の最中に主人公・宗介の母、リサが50MHz帯のアマチュア無線で内航船の船長である夫に連絡を試みる場面がある。応答は得られないが、息子・宗介は沖合の父の船に向けて発光器を使い、モールス信号を送信する。リサの依頼で送られた信号は“BAKA… BAKA…”というユーモラスな内容で、高速で打たれる様子が描かれている。
https://amateurmusenshikaku.com/ponyo/
実際の無線通信の原理を踏まえて描かれている点は興味深い。50MHz帯(6mバンド)は国内短距離通信に向く一方、Eスポ(スポラディックE)による遠距離伝搬の可能性もあり、嵐の描写と合わせて「通信困難な状況」を表現。発光器を用いたモールス信号も、光を媒介とした古典的通信手段としてリアリティがある。
ジブリ作品には他にも無線描写が散見される。『天空の城ラピュタ』ではムスカ大佐がモールス送信を行い、『紅の豚』ではポルコ・ロッソが発光信号を駆使して敵に降伏勧告を行うのだ。これらは、無線家にとっては思わずニヤリとさせられるアニメならではの愉快な演出である。
ミームいろいろ夢の旅
80年代の科学教育アニメ『ミームいろいろ夢の旅』の第73話「宇宙からのメッセージ!?」(1984年9月2日放映)では、『ちびまる子ちゃん』よりも、アマチュア無線の仕組みや災害時の役割が技術研究的な面で詳細に描かれている。

小学生の主要キャラが実際のアマ機を操作し、14MHzでのオペレートをそつなくこなす描写は度肝を抜かれ、当時のアマチュア無線教育的価値も高い。しかし、放送当時からハム界隈でほとんど知られていなかった点は謎であるし、現代でも知名度は低い。
理由として、キャラクター表現が“萌え”文化的要素に欠けることや、当時のメディアでの紹介が限定的であったことが考えられる。各種配信サービスでの配信と、当サイトでの紹介により、ようやく技術的価値が再評価されつつある昨今である。
逆に“非科学的”な当サイトが紹介してしまったことで、アマチュア無線界隈の(科学的な)大御所サイトが紹介できない可能性あり。
💡 補足:各方面に、すいやせん。
ちびまる子ちゃん
90年代に放映された『ちびまる子ちゃん』の回「まる子、アマチュア無線にあこがれる」は、ハム界隈で広く認知されている。作品内で、まる子が同級生の長山くんの自宅でアマチュア無線に触れ(見学)、操作や交信の楽しさ(見学)に目覚める描写は、子ども視点でアマチュア無線の魅力を伝える稀少な例であった。

実際、原作の故・さくらももこ氏自身がハムである。
💡 補足:1998年当時の、『CQハムラジオ』誌にて、ちびまる子ちゃんとコラボしている。
✅アマチュア無線など趣味の無線とキャラクター
武部 沙織
「ガールズ&パンツァー」に登場する女性キャラクター。2アマを取得している。
無線ガールズ
icom(株)が「無線ガールズプロジェクト」として、自社製のベストセラー受信機「IC-R6」を擬人化。アイコム関連のアマチュア無線ショップ「デジハムサポート」が直接的に展開。

主要メンバーには『Kira』『Akane』『Sora』(さらに「IC-R15」モデルの『Yuki』も登場)がおり、それぞれIC-R6のカラーバリエーションに対応した衣装を纏っている。
デンパくん
総務省総合通信局が周波数の適正利用を広めるために生み出した公式キャラクター。電波利用の象徴としてデザインされ、ポスターやイベントに登場するだけでなく、着ぐるみまで製作されたあたり、役所の本気度と予算の使いどころに独特のセンスを感じさせる。
その存在は、警視庁の「ピーポくん」に近い“官製マスコット”枠に収まるはずなのだが、電波行政という一般人には実感しづらいテーマを啓発するために作られた結果、どうしても「誰に向けているのか分からないキャラ」としてネタ視されがちである。
一般にはほとんど馴染みがなく、イベントで唐突に現れるデンパくんの着ぐるみを見て「これ誰?」と首を傾げる光景は定番。
結局のところ、デンパくんは無線愛好家や行政広報ウォッチャーの一部では「電波を正しく使いましょう」というお堅いスローガンを、ほんのり間の抜けたマスコットに託すことで、“国が生んだ電波系ゆるキャラ”としてシュールな存在感を放っている。
電波りようこ
総合通信局の公式萌えキャラ。周波数の適正利用を広めるため、総務省総合通信局に爆誕した広報キャラクターである。名前の由来は「電波利用」をもじったシンプルなものだが、そのビジュアルは妙に“萌え寄り”で、2000年代初頭の広報キャラとしては異彩を放っていた。
一般的には啓発キャンペーンのパンフレットやポスターに登場しただけの存在であったが、アマチュア無線愛好家や受信マニアの一部には、これを単なる広報素材としてではなく“萌えキャラ”として楽しむ層が出現した。
彼らはパンフレットを保存用・観賞用に複数部集めたり、配布先の総合通信局に直接問い合わせをしたりと、通常の電波行政資料とは明らかに異なる「収集対象」として扱った。
その後、インターネット掲示板や同人誌で「電波りようこ」を再解釈するファンアートが散発的に登場し、“電波系キャラ”の元祖的存在として再評価されることもあった。特に「公務員萌えキャラ」というギャップに惹かれる層には、今なおカルト的な人気がある。
もっとも、公式としては単なる啓発マスコットであり、キャラクター展開が本格化することはなかった。そのため現存する資料は少なく、コアなマニアにとっては「幻の広報キャラ」として希少価値が高い存在となっている。
あいつと俺
『あいつと俺』は1980年に制作され、1980年から1984年にかけて東京12チャンネル(現・テレビ東京)で放送された刑事ドラマである。主人公の峰山凡太郎を名優・川谷拓三が演じ、相棒の山田平太を清水健太郎が務めるバディもの。
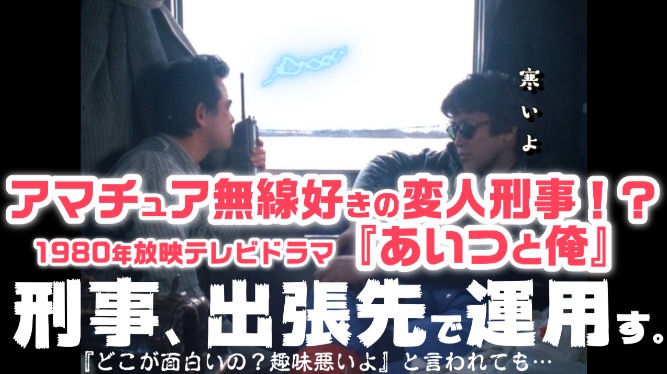
峰山刑事は、アマチュア無線を趣味とする“変わり者”として描かれている。劇中では、捜査の合間に無線機を操作して交信を楽しむシーンがあり、CQの出し方、コールサインのやり取りなどが細かく描かれていた。
峰山の無線趣味は刑事としての堅苦しさだけでなく、遊び心や人間味を視聴者に印象づける効果もあった。無線を趣味とする視聴者にとっては、自身の楽しみを共有する感覚や、時代背景を知る手掛かりとしても興味深い描写である。
ただし、峰山への同僚刑事からの目は「どこが面白いのそんなの。趣味悪いよな」などといった具合に、あたりは強い(!?)























































































































